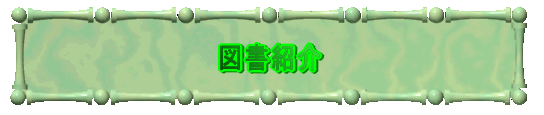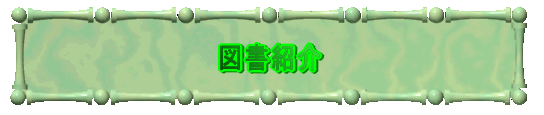持続可能な社会(Sustainable society)へ向けた
温暖化と資源問題の現実的解法 御園生誠 著
平成20年8月20日 発行
発行所 丸善 株式会社
定価 (本体1,800円+税)
本書は地球温暖化問題について、環境、資源、エネルギーの諸問題を解決し、豊かで持続可能な社会を築くことが人類の最大の課題だとし、世界の現実を冷静科学的に理解し、それに基づいて真の持続可能な社会を構築するための健全な対策を立てる必要があると説く。
本書の提言は、温室効果ガスの低減に関して、チャレンジングな目標が提案されているが、これらの目標設定に相当な無理があること、また重要な対策のいくつかが、具体性が乏しく実現が難しいだけでなく、拙速に実施するとかえって事態を悪化させかねないので、目標設定の前提や手法を見直して、対策の優先順位、実施時期を改めた実施計画を策定すべきであるとする。
その場合、一挙に脱炭素社会《=脱化石資源(メモ参照)》への移行を求めるのでなく、化石資源の有効利用による消費抑制と原子力の活用を軸とし、他の資源を活用する「準・低炭素社会」を経由してから徐々に21世紀後半に低(脱)炭素社会(化石資源を大幅に抑制)に移行することを目指すべきであり、その際、地球温暖化対策つまりエネルギー問題が要求する技術革新だけでなく、生活スタイルの変革(エネルギー以外の多様な資源それぞれの量的・質的な特徴を活かしたバランスの良い使い方、および過剰な消費を抑制した今までとは異なる生活スタイル)を目指すべき、と言うのが本書の基本的スタンスである。
京都議定書の一番の問題点は、条約加盟国の温室効果ガス排出量が、世界の30%程度しかカバーしていないことである。中国・インド、その他途上国は対象外であるうえ、最大の排出国である米国が離脱した。また1990年を基準年にしたため、それ以前に省エネルギーの実績を上げた日本が不利になったことも大きな問題である。
米国発の金融危機に端を発する世界不況と日本の政冶の閉塞感に問題がかすみがちだが、ポスト京都議定書枠組みをめぐる世界の外交合戦は益々重要性を帯びてきている。米国はオバマ政権になると京都議定書の基準年を採り入れた中期目標を掲げるようであるが、各国・地域が国益を賭ける「ポスト京都議定書」のパワーゲームで不利なシナリオも予想される日本は益々戦略的な交渉力が求められているようであり、その論拠としても本書が役に立つことを期待したい。
|

著者略歴
1961東京大学工学部
応用化学科卒、
1966工学博士、
1983東京大学工学部教授、
1999工学院大学教授、
東京大学名誉教授、
2004年度日本化学会会長、
2005より(独)製品評価技術基礎機構(NITE)理事長、
2008より日本化学連合会会長、日本工学アカデミー副会長。
メモ
化石資源は主として炭素Cと水素Hからなり燃焼すると二酸化炭素と水になり熱を出す。一般に石炭・石油・天然ガスをさす。
化石資源以外のエネルギー源としては、原子力のほか新エネルギーといわれるものとして、バイオマス《①材料資源系(木材・紙・ゴム・繊維など)②食品系(穀物・家畜・油脂など)③廃棄物系(廃棄紙・家畜排泄物・生ゴミ・廃木材・下水汚泥など)④未利用系バイオマス(間伐材・稲わら・落ち葉・建築廃材など)⑤エネルギー作物系(トウモロコシ・サトウキビ・菜種など)》燃料・地熱エネルギー、小規模水力発電、風力発電、太陽エネルギー(太陽電池、太陽熱など)、海洋エネルギー(温度差発電など)がある。
|