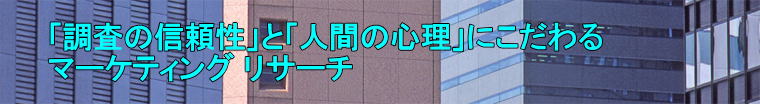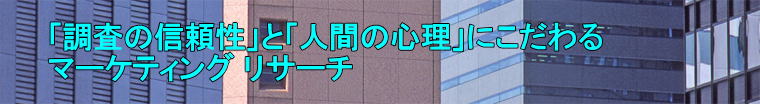◆ 調査の信用・信頼を失う事例 ◆
調査は、調査会社での各作業が的確・公正・精確に行われ、そして、クライアントでその調査結果が正しく利用されて、初めて信用・信頼を得ることができるのです。
ところが、現実には、調査会社とクライアントの双方で「調査の信頼性」を失うような出来事が起きています。
● 調査会社で起きる調査不信
調査会社が PowerPoint を駆使して、どんなに素晴らしいプレゼンテーション資料や報告書を作成しても、その調査が 調査設計 → 調査票作成 → 実査 → 集計 → 分析
→ 報告書作成 のいずれかの段階で致命的なミスを犯していると、全く役に立たない調査結果を提出することになります。
● クライアントで起きる調査不信
調査結果を利用するクライアントにおいても、調査の本質を知らないブランド担当者や経営幹部による調査結果の恣意的な解釈や、調査結果を軽視・無視した判断・決定によって生じた不都合が、「調査」自体の問題 として誤解されてしまうことがあります。
この < 【A】 「調査不信」を招く諸問題 > では、「調査不信」を招く各種の事例をご紹介しています。
・ A-1 調査理論と現実のギャップ
・ A-2 低出現率の調査を低予算で実施
・ A-3 質問文に左右される調査結果
・ A-4 不都合な調査結果は無視
・ A-5 調査・統計データへの疑問
※ このパートは項目の性質上、調査の問題点ばかりを取り上げています。
そのため、調査への不信感を煽るのではないかと、不安を抱かれる方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、たとえ一握りとは言え、このような問題を引き起こす心ないリサーチャー、調査員、マーケター、経営幹部が存在するために調査不信を招くわけですから、敢えて、俎上に載せることにしました。
勿論、大多数のリサーチャー、調査員、マーケター (*) 、経営幹部の方たちは、調査への見識や良識を持たれた方であるということを申し上げておきます。
(*) : ここではマーケターを、次のように定義しています。
企業や団体の中で、’マーケティング ’を管理する職、あるいは、その部門。
リサーチャー は「理論的な思考」や「物事の本質を見通す分析力」が求められるのに対して、
マーケター は「豊かな発想力」や「創意工夫」が求められる。
|
|