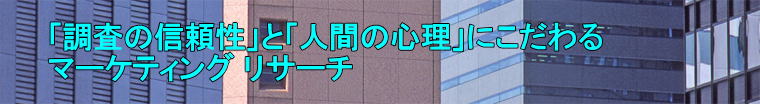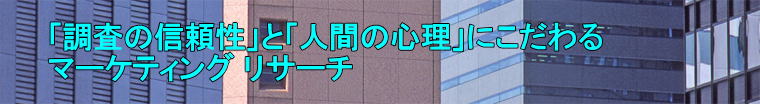◆ 実情に即さない「調査理論」が調査員の不正を招く! ◆
日銀が実施した意識調査で「虚偽回答」が発覚!
日本銀行が実施した生活意識調査で、調査の信用・信頼を失墜させるような出来事が起きました。 2005年7月、ある男性から日銀に電話があり、「調査を受けていないのに、調査報告書が送られてきた」と言ってきたそうです。
この調査は訪問調査で実施されましたが、実情を調べてみると、調査員が調査会社から与えられた名簿で指定された男性に会えなかったため、同年代の別人を対象者にしてしまったことが判明しました。 つまり、指定された調査対象者に会えたかのような調査票を作り上げ(業界用語で「メーキング」というが、これは和製英語)、それを調査会社に提出したことによって起きた問題です。
有効回答の全票を追跡調査で再点検!
クライアントである日銀の調査担当者は有効回答とされた2,997票について、調査会社に追跡調査を求めたそうです。 その結果、本人が回答していない、または、その疑いが残るものが235票あったそうです。
同じ頃に実施した政府広報室などの調査でも不正が見つかり、その調査会社は国から4ヵ月の指名停止になったそうです。
【 2008年12月10日 朝日新聞 夕刊 : ニッポン 人・脈・記 - 民の心を測る⑨ 】 より引用
|
◆ 調査実施者の実情認識に甘さがなかったか!? ◆
この虚偽回答の出来事を知って、私がまず気になったのは以下の点です。
① 調査会社は、「調査員教育」 や 「インスペクション (回収票からの抜取り
検査)」 を厳格に行なっていたか?
② 調査員の仕事に対する 「責務感」 は、どの程度のレベルだったか?
③ 調査会社は調査環境の悪化を認識し、その対策を考えていたか?
④ クライアントの調査担当者は、調査現場の実情(調査員が指定された調
査対象者に会う困難度)を理解・認識していたか?
虚偽回答を招いた主要因は何か?
このような問題が発生した背景には、次の2点が主因として考えられます。
● サンプリング理論が、調査環境の悪化で適応できなくなった!?
ひとつ目の問題点は、サンプリング(標本抽出)理論が重視され、調査環境の悪化は軽視されていたことです。
この虚偽回答が起きた頃の調査現場には、次のようなことが原因で「協力率(回収率)」の低下が顕在化していました。
◇ 在宅率の低下 ・・・ 平日はパートや各種の会合に出かける主婦が多くな
り、週末は家族とレジャーなどで外出する頻度が高くなった
◇ 拒否率の上昇 ・・・ インターフォン、カメラフォン、オートロックなどの普及
で、断わりやすくなった
◇ 個人情報保護法の施行によるプライバシー意識の向上
● 安売り競争が虚偽回答を招いた!?
ふたつ目の問題点は、入札で値下げ競争を煽られたため、調査会社が仕事を取りたい一心で、調査の難易度に見合わない廉価で応札したことです。
その安売り競争で、次のような負のスパイラルが待ち受けていたと思います。
▷ 調査員に難易度に見合った手当てが払えない
▷ そのため、調査員に対して弱腰になり、正当な指示も強く言えない
▷ 調査員は回収率を高めるためにコールバック(再訪問)の励行を指示され
ても、一票当りの完了手当とのバランスを考えてしまう
▷ コールバックをしないと完了票数が減り、調査員の収入が少なくなる
▷ 不心得な調査員は完了票数を増やすために、虚偽回答という不正に奔る
このように現実に即さない調査理論(ここでは対象者抽出方法)と調査員手当が、調査の精度を歪める原因を作り、調査会社やクライアントが自らの手で「調査の信頼性」を失う事態を招いてしまいました。
サンプリング理論の破綻は、20年前から前兆があった!
この虚偽回答が起きたのは2005年でしたが、私が調査会社で実査部に所属していた1986年(昭和61年)頃、つまり約20年も前から調査の現場ですでに前兆が現れていました。
訪問調査で、事前に準備された名簿をもとに対象者に会うという方法は、調査理論に基づいてはいます。 しかし、当時、すでに実情に即さなくなりだしていたため、心ない調査員の不正行為が懸念され、私はこの方法は早晩行き詰まると予想していました。
このような問題に対しては、調査業界はクライアントと協議を行い、早めに改善策を考えるべきです。
|
☞ 社会環境の変化に即応した「実査方法」を採用する!
「調査の信頼性」を保つためには、「人間の心理」(ここでは調査員の心情)をもっと重視すべきです。 そして、社会環境の変化に即した調査・実査方法にシフトしていく勇気や決断と、調査の難易度に見合った実査費を計上することが必要です。
また、安売り競争に気を取られていると、日本の 「調査の信頼性」 はいつまでも向上しないので、調査会社はクライアントと共に、この点もしっかり考え直すべきです。
|
|