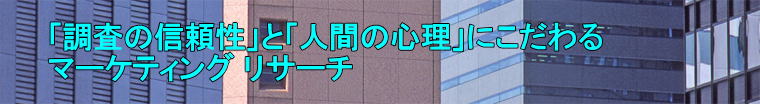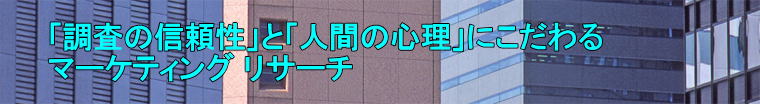◆ 調査・統計データの問題点を見極める! ◆
世の中には公表されている調査・統計データが色々あります。
総務省統計局をはじめとした官公庁の調査結果、あるいは、企業・団体が自社の商品やサービスについて行った意識・実態調査の結果をパブリシティとして公表したものなどがあります。
また、最近はマスコミ各社が世論調査を頻繁に行い、内閣支持率や政党支持率の結果などをテレビ番組や新聞記事で伝えています。 ちょっと変わったところでは、時の人の行動や態度に関する賛否や支持(期待)度など時事ネタを扱った、インターネット調査の結果もあります。
ところが、このような調査・統計データの中には、疑問符が付いて気になるものも存在します。
|
■ 「世論調査」に若い世代の意見が反映するのか!?
調査(実査)を2日間くらいで実施して、その結果を1~2日後に公表する世論調査は、通常、コンピューターで無作為に選んだ番号にかける電話方式で行われています。
その番号は調査対象者の居住地域(都市)が分かる家庭の固定電話が対象のため、携帯電話しかない世帯は対象外となります。 そのため、携帯派が多い若い世代の意見・考え方は、調査結果にあまり反映されないという欠点があります。
ところが、選挙直前に行われる ’世論調査の政党支持率 ’と ’選挙結果’にあまり乖離が生じないのは、そもそも若い世代の投票率が低いことに、その要因があると考えられます。
このように、若い世代の意見が反映していない(?)と思われる調査結果が、独り歩きしています。
ところが、インターネット調査は電話調査とは逆で、パソコンが苦手、あるいは、所有していない人の割合が高い高齢者の意見が、調査結果に反映しにくくなります。
■ 家計簿をつける人の偏りが気になる「家計調査」!?
総務省が実施している調査の中に「家計調査」があります。 この調査の目的は、国民生活における家計収支の実態を把握し、国の経済政策や社会政策を立案する基礎資料にするためということです。
この調査の対象となった家庭は、家計簿の内容を見て調査票に回答するそうですが、ここに懸念点があります。 昔は家計簿をつける家庭が多かったため、調査対象の世帯を平均的にサンプリング(標本抽出)することが出来たようですが、近年、家計簿をつける世帯が偏ってきたため、サンプル自体も偏りが出ているのではないかと懸念されています。
そうなると、家計簿をつけるという、例えば、几帳面な人の特性が出やすくなるため、このような統計データを拠りどころに、計画の立案を行ってもいいのかという疑問が起きてきます。
■ 「キャリーオーバー効果」 を意図的に使った調査!?
調査には 「キャリーオーバー効果」 というのがあります。 これは調査対象者が質問に回答していくうちに、その調査の ’前半 ’の質問で知り得た内容から作り上げられた観念や見方が、’後半 ’に出てくるその調査の本当のねらいである質問の答えに影響を及ぼすことで、オーダーバイアス(順序による偏り)の一種です。
例えば、’消費税 ’に関する調査を行う時に、次の2通りのアプローチが考えられます。
① は 人口構成の将来的な変化 -> 国の財政事情 -> 社会保障の実情 ->
諸外国における社会保障の状況 (税金は高いが、医療や高齢者介護の制度が充実) といった関連質問を行った後に、「消費税率を 5% から XX% に引き上げるという計画があります。 あなたはこれに賛成ですか、それとも、反対ですか。」とい
う本題質問を行う
② は 本題質問を先に行ってから関連質問を行う
この場合、消費税率のアップに賛成する割合が高くなるのは ① です。
それは前半の関連質問で、消費税率をアップしないと財政はいずれ破綻してしまう、あるいは、恵まれた社会保障制度をつくるためには消費税のアップはやむを得ないという印象を与えるので、最後の本題質問の結果は当然 ’賛成’が多くなります。
一方、② は、消費税率をアップしない場合の影響や、アップした場合の効果についての理解が不十分な前半で本題質問を行うため、かなりの人が基本的には増税を歓迎しないことから反対の意見が出やすくなります。
このような方法を意図的に使って、調査の実施者にとって有利・好都合な結果を得ようとする調査がありますから、常に、問題意識を持って質問の内容や順序を確認することが大切です。
|
☞ 調査・統計データの「信頼性」の鑑識眼を習熟する!
このように調査・統計データの中には、疑問符の付くものが多々あります。
しかし、調査にかなり精通していないと、問題点の発見や信頼性の見極めは難しいと思います。 従って、調査・統計データを見る時はあまり鵜呑みにしないで、ひとつの傾向を知るという程度に止めておくことです。
ところが、従事されている仕事によっては、調査・統計データを何かの説明資料などに引用することもあると思います。 そのような方は、日頃からデータの信頼性を鑑識する習慣を身につけておくことが必要です。
例えば、その調査は、どのような条件で実施されたのか、内容確認をしっかり行うことです。
◇ 誰が (実施した官庁・企業・団体は?)
◇ いつ (何年何月何日頃?)
◇ どこで (調査地域は?)
◇ 誰に (調査対象者の性・年令・職業は?)
◇ どのような方法 (インターネット、訪問、電話といったアプローチは?)
◇ どのような調査票 (質問内容と質問順序は?)
◇ 調査内容や結果が、調査実施者にとって有利・好都合なものになって
いないか?
もし、このような要件が不明確なデータは、使用を控えた方が無難です。
|
|