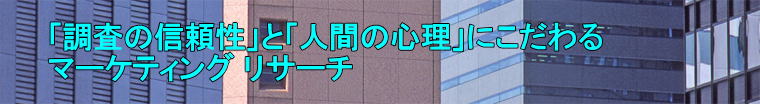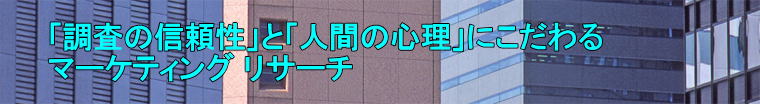◆ マスメディアの報道姿勢から教えられた「調査の中立性・公平性」! ◆
ちょっと古い話ですが、1967年(昭和42年)頃、在京のテレビ局が行った「人間の心理」に関する調査結果を紹介した新聞記事に、当時、報道カメラマンだった私は大変興味を感じました。
それは、ニュース素材の編集の仕方(つまり、映像の見せ方)ひとつで、そのニュースを見た視聴者の感想や印象が変わるという内容でした。
ふたつのグループに、異なる刺激物(デモの様子)を見せて反応を調査!
1967年頃から反戦運動や学園紛争に関連した学生運動が盛んとなり、羽田・新宿・お茶の水などで学生デモ隊と警察官の衝突が頻繁にありました。
そこで、マスメディアの中立・公正性を保つために、デモの様子をどのように撮影・編集して、ニュースで放映すればよいかを確認するために、次のような調査を行いました。
① 過激なデモの様子を撮影したフィルム(当時はビデオでなく16mm生フィル
ム)を使用して、2通りの編集方法でテレビのニュース風に仕立てたものを
制作した
② 2通りの編集方法は、次のような内容だった
(A)篇 : 学生デモ隊が警官隊に追われて逃げる中、捕まって暴れる学生
が警官に警棒やジュラルミンの盾で叩かれたり、足蹴りされているシーン
などを中心にまとめたもの
(B)篇 : 本隊から離れて警備していた警官が学生デモ隊に襲われ、ゲバ
棒でメッタ打ちにされ、顔から血を流して路上に倒れているシーンなどを中
心にまとめたもの
③ 一般視聴者を、グループ構成(性・年令・職業など)が等質になるよう配慮し
ながら2グループに分け、それぞれを別の調査会場に入れた
④ ひとつのグループには(A)篇のフィルムを、もうひとつのグループには(B)篇
のフィルムを見せた
⑤ 映写後、そのフィルムの内容に関する調査を行った
刺激物の内容の違いに適合した調査結果の差!
調査結果は、学生デモ隊や警官隊への同情的な評価や意見が、(A)篇を見たグループでは学生デモ隊に、そして、(B)篇を見たグループでは警官隊に高かったそうです。
当然の結果かもしれませんが、テレビ局はこの調査結果を見て、現場での撮影時やフィルムの編集時に、中立性・公正性への配慮が重要だということを肝に銘じたそうです。
調査でも「中立・公正」の精神が求められる!
このテレビ局が実施した調査の結果は、刺激物の違いで受け手の反応が変わることを証明した適例ですが、マーケティングリサーチにおいても同様のことが言えます。
調査票の「質問文」や「提示物」の内容で、調査結果はいくらでも変わりますから、調査票の作成には慎重な作業が求められます。
余談になりますが、報道カメラマン時代に学習したこの「中立・公正」の精神は、後に調査の世界に入ってからも、私にとって大きなバックボーンとなりました。
【 関連項目 : ★ 私の履歴書 ★ - 報道カメラマン時代 】
|
☞ 調査票や提示物にも「中立・公正」が求められる!
デモを題材とした「人間の心理」に関する調査は、調査票や提示物(刺激物)の内容が調査結果に大きな影響を与えることを証明しました。
マーケティングリサーチにおいても、調査票(質問文・選択肢)や提示物(製品説明書)の内容が、調査結果に影響を及ぼすことがあります。
調査結果は重要な判断や決定に使われますから、調査会社の担当者が私意を差し挟むことや、クライアントのブランド担当者などが調査票の内容に恣意的な要求を行うことは、あってはいけないことです。
調査は常に 「中立・公正」 が求められています。
|
|