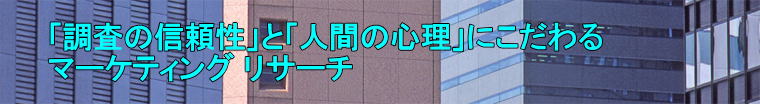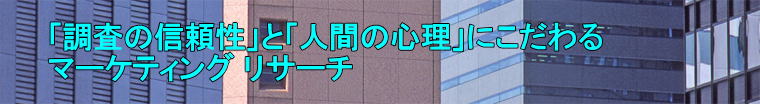☞ クライアント側もリサーチャーとしてのプライドを持とう!
クライアント時代は、対外的には調査会社と仕事をした時の苦労や喜び、また、対内的にはブランド担当者と仕事をした時の苦労や達成感、あるいは、経営幹部から依頼や相談を受けた時の苦労や充実感 といったことが回想されます。
社内の人たちとリサーチャーとしての良心の中に葛藤が生じたことも多々ありましたが、そのような経験が私に強固なリサーチャー精神を植えつけたと思います。
クライアント側にいても、調査会社と仕事の内容について対等な議論ができ、また、社内でも信頼される調査担当者(リサーチャー)となるために、プライドを持って毅然とした態度で仕事に臨むことが重要です。
|