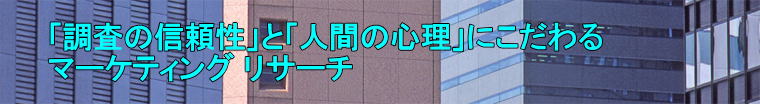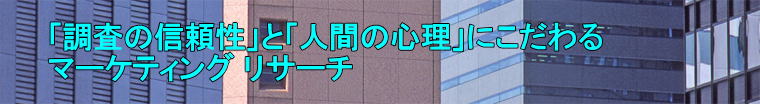◆ インターネット調査の長所と短所 ◆
インターネット調査には、次のような長所と短所がありますから、その性質を十分に理解・認識された上で、利用してください。
<長所>
◇ 実査に要する「時間」と「費用」が、他の調査方法に比べて格段に優位で
ある
◇ 多数の調査対象者に一斉に配信(コンタクト)できる
◇ 出現率の低い調査対象者を容易に探すことができる
◇ 訪問調査のように調査員が介在しないので、人間によるミス(聞き間違い、
記入間違い、勘違いなど)やバイアスの心配が少ない
◇ データの回収と集計ソフトが直結するので、集計期間を短縮できる
◇ 対象者は登録モニターなので、調査依頼がきた時に心の準備ができて
いるため協力率が高い
<短所>
◇ サンプリング理論が通用しないため、「代表性」について統計学的な保証
が得られない
◇ 母集団の名簿として使えそうなものがないため、「精度」に関して疑問を
持たれる
◇ モニターは希望者を募集するので、サンプル(調査対象者)としての「無
作為(ランダム)性」がない
◇ インターネットの利用者で、かつ、調査モニターの登録者に限定される
◇ インターネットの利用者数やモニターの登録者数に、性・年令などで偏り
がある
◇ 回答時の調査対象者の「本人確認」が不可能なため、「なりすまし」(例:
夫婦の間で、妻が夫の代わりに回答、あるいは、その逆など)の危険性
がある
◇ パソコンを相手に回答するため、調査対象者の良心に頼るしかない
◇ 調査対象者に小遣い稼ぎの意識が高まると粗製乱造的な状態が生じ
て、「調査の品質」の低下を招きかねない
◇ 調査対象者が何回も協力することによって慣れが生じたり、事前準備
(認知・購入銘柄の学習)をしてしまう
以上がインターネット調査の長所・短所ですが、今のところ、「速い」、「安い」の長所が優先されており、調査の本質を歪めかねない欠点の部分は、ほとんど軽視・無視されているのが実情のようです。
|