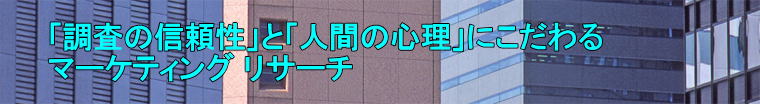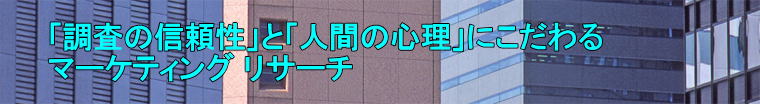◆ 消費者の生の声は、リサーチャーやマーケターの栄養剤! ◆
オブザベーションには、目的意識をしっかり持って行こう!
定性調査での座談会(グループインタビュー)は、通常、調査対象者は1グループ6~8名で、1プロジェクト3~6グループで実施されます。
この座談会をオブザベーション (*) していると、調査対象者(消費者)の色々な発言の中からキラッと光る意見が出て、時には、’目から鱗が落ちる’思いを経験できます。
(*) インタビュールームに隣接した部屋からハーフミラー越しに観察、あるいは、
別室にある複数台のモニター画面で視聴
定性調査(座談会 / One-on-one インタビュー)は、次のような目的で行われます。
● クライアントが定量調査に使用するコンセプト(製品説明書)やテレビCM 案
などを調査対象者(消費者)に見てもらい、主に次のような点を確認する
◇ 消費者が正しく理解できるか?
◇ 魅力に感じる点はどこか?
◇ 分かりにくい点はどこか?
◇ 改善したらもっと良くなる点はあるか?
● 既存ブランドの新たな方向性を考える際、ブランドイメージ、長所・短所、改
善希望点などで現状把握を行う
● 新製品の売上げが伸び悩んでいる時、あるいは、既存ブランドの力が低下
している時、色々な側面から確認をして低迷・不調の要因を探り出す
● 新製品や新しいカテゴリーで商品を開発しようとする時、消費者が求めてい
るニーズ ( Needs ) やウォンツ ( Wants ) を探り出す
オブザベーションを有効活用するためには、その座談会の目的、テーマ、質問項目、質問フローを事前に確認・把握しておくことが大切です。
定性調査でのインプットは、定量調査にも活用できる!
座談会で、コンセプトや製品の評価理由、銘柄選定理由、テレビCM の好嫌理由などを聞いていると、ブランド担当者や広告代理店のクリエーターがベストと思っているコンセプト案やテレビCM 案に対して、消費者目線での厳しい評価・指摘が色々出てきます。
この定性調査で出てくる ’肯定・否定 ’の様々な意見や評価は、マーケターやクリエーターだけでなく、リサーチャーにとっても大変役に立ちます。
それは定量(量的)調査の準備段階や分析段階においても、有用な知見となるからです。
▷ 「調査企画書」作成時のアイディア
▷ 「調査票」作成時の留意点
▷ 「調査結果」の分析時の視点・ヒント
▷ 「調査結果」と「消費者心理」の関連性を見つける時の糸口
自分の担当プロジェクト以外でも、対象者条件の異なる座談会がある時は、積極的にオブザベーションされることをお勧めします。
また、クライアントの調査担当者やブランド担当者も、自社のプロジェクトがある時は、消費者の生の声を出来るだけ多く聞いて、自社ブランドの姿を正しく理解するために役立ててください。
|