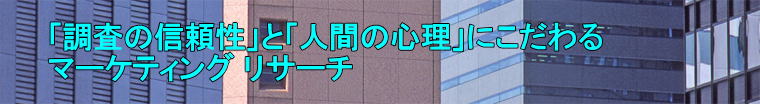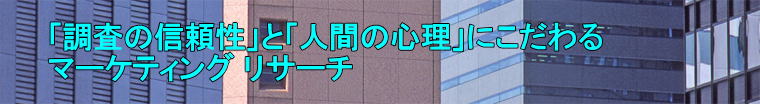◆ 文字ではなくて「色彩」で注意の喚起! ◆
人間は色彩によって、色々な反応や判断をしたり、感情や気分を抱きます。
例えば、「赤」色を見れば、瞬間的に注意・危険・不安なイメージが湧き、行動には緊張感や慎重さが出てきます。 一方、「青」色を見れば、安全・安心・清潔なイメージが湧き、行動には冷静・落着きなどが期待できます。
調査でも調査票作成や会場調査の管理において、「色彩」による管理方法を取り入れれば、視覚的な判断も加わるため作業ミスが減少したり、調査員や調査対象者の気持ちを落着かせたり集中させることに役立ちます。 その結果、調査の「品質」や「精度」の向上も期待できます。
そこで、色彩心理を応用した事例を、ご紹介しましょう。
首都高速が交通安全対策に「赤色カラー舗装」を採用!
下の写真は東京の首都高速道路 都心環状線の「銀座」出入口付近です。 この道路の路面が赤色にカラー舗装してあるのは、どのような目的のためだと思いますか。
この場所を走行された方、あるいは、テレビ朝日の 「スーパーモーニング」 をご覧になった方は、すでに、その目的や効果をご存じだと思いますが、今、初めてこの写真をご覧になった方は、その目的をちょっと考えてみてください。
【 ヒント 】 この都心環状線の新富町-銀座-汐留付近は、昔、築地川があった所を改修して、このように高速道路を作りました。 そのため、厳しい道路の線形(勾配やカーブなど)、あるいは、橋梁や短いトンネルが断続的にあります。
考え中 => 考え中 => 考え中
 ( 写真 A ) ( 写真 A )
 ( 写真 B ) ( 写真 B )
まず、場面の説明をしましょう。
(写真 A)
左側の車線(車両が走り去って行く)と右側の車線(車両がこちらに向かって来る)の手前3分の1くらいの所で、路面が通常の「墨色」から「赤色」に変わっています。
そして、左側の車線で見ると、この赤色の部分に入った80mくらい先(橋梁が見える所)から急カーブが始まります。
(写真 B)
どちらの車線も、後方にあるトンネルの20mくらい手前から、路面が「赤色」に変わっています。 これを右側の車線(車両がこちらに向かって来る)で見ると、写真の右下方向に進むと急カーブが始まります。
※ お時間のある方は、URL が 【 http://www.shutoko.jp/topics/index.html 】
首都高速道路(株) Corporate Information の中にある < 新聞・テレビで話題! 「赤い首都高」 ~首都高の交通安全対策~ > も、参考にご覧ください。
「赤色」のカラー舗装が、圧迫感のある道路で心理的ブレーキ!
目的や効果は、お分かりになりましたか?
この「銀座Sカーブ」と呼ばれる付近は、スピードの出し過ぎによるカーブでのスリップ事故が多発していました。 そこで、事故防止対策として、カーブの形が目立つように路面を赤色にし、かつ、通常の路面より滑りにくくしました。
川を改修して道路を作ったため、急カーブ・短いトンネル・橋梁が断続的に続き、また、かつての川底を走行するので壁面が非常に高くなり圧迫感があります。
そのような悪条件下で、見通しの良い道路と同じ感覚でスピードを出していると事故も起きやすかったようです。
そこで、看板(つまり、文字)による注意喚起だけでなく、新たな事故防止対策として登場した路面を「赤色」でカラー舗装にするというビジュアルでの工夫(刺激)が功を奏したようです。 それは「赤」という色が 「危険」な状態を想起 -> 心理的なブレーキ -> 安全なスピードに減速 という思考・行動を引き起こすからでしょう。
現地走行で心理的効果を体験!
私自身が、このようにカラー舗装化されたことを知らないで、初めてこの場所を走行した時、次のような思考・行動が瞬時に行われていました。
赤色にカラー舗装した路面が目の前に迫ってきた時、「何だこれは!」と驚くと同時に、「何か危険地帯(区間)であることを知らせているな?」という考えが直観的に働き、いつの間にかスピードを落していました。 まさに、「人間の心理」を考えた素晴らしい工夫(アイディア)だと感心しました。
カラー舗装化で、事故の発生件数が半減!
このカラー舗装工事は、外回りは平成20年12月、内回りは平成21年2月に実施したそうですが、外回りでの事故の発生件数を工事前(平成20年1~5月)と工事後(平成21年1~5月)で比較すると、30件から15件に減少したそうです。
通常の舗装路面より滑りにくくしたことが減少の一助になったとは思いますが、やはりビジュアルでの注意の喚起、あるいは、心理的効果が大きく貢献したと考えられます。
しかし、ひとつ懸念されることは、この地点を頻繁に走行するドライバーは、慣れからくる緊張感の緩みで減速する意識が薄れることです。 初めて走行した時の気持ちを、いつまでも忘れないでほしいと思います。
◆ 調査でも「色彩効果」の応用が、ミスや勘違いの防止に役立つ ◆
調査の話から逸脱しましたが、ここでのポイントは「人間の心理」を考えた工夫ということです。 路面を赤色に変えるという、考え方としては大変シンプルな発想ですが、この程度なら「人間工学」に関する高度な専門知識がなくても、考えることができる範囲だと思います。
この首都高速道路の事故防止対策を「調査」に当てはめて考えると、赤色にした路面は「調査票」や「提示物」などであり、車のドライバーは「調査員」や「調査対象者」です。
調査においても、このような「色彩効果」を応用して色々な工夫を凝らせば、調査員や調査対象者のミスや勘違いを防止したり、【 G-2 : 送り手の誠意が伝わる調査
】 の「新たな郵送調査」において既述したように回収率の向上に役立つと確信しています。
|
|