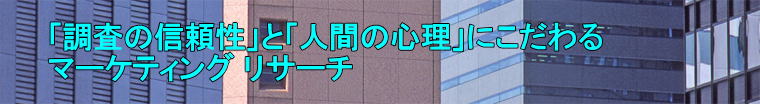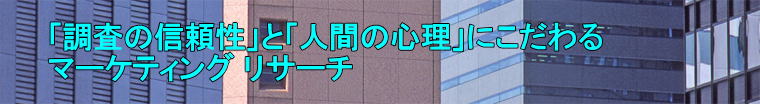◆ 調査は ’数字が命’! ◆
どんなに優れた調査手法や分析手法で調査を行っても、調査票、コンピューター・アウトプット・テーブル(集計表)、プレゼンテーション資料、最終報告書などで 「致命的ミス」 や 「初歩的ミス・単純ミスの繰返し」 があると、クライアントからの信用・信頼を失います。
特に、ひとつの調査の主要目的において重大なミスが見つかると、その調査結果の全てに不信感を抱かれるので、真剣な取り組みが求められます。
調査の 「ミスの防止」 には、経営幹部の危機意識が必要!
ミスを防止するためには、調査会社の経営幹部の方が、次のような点に気を配ることが大切だと思います。
◇ 調査会社が ’数字 ’の過ちをおかすことの重大性を認識する
◇ 社員に ’数字 ’ の重要性を教育・徹底する
◇ 精神論だけでなく、方法論(チェックシステムやサポート態勢)も確立して、
徹底する
経営幹部の方たちは売上げの数字に頭が行きがちになりますが、まず、調査会社としての基本的な部分を等閑(なおざり)にしないでほしいと思います。
チェックシステムやサポート態勢がしっかりと確立・徹底できれば、自ずと、業績の向上に繋がっていくはずです。
経営幹部が 「ミスの防止」 に無関心だと、社員にも蔓延する!?
私が発注者(クライアント)側にいた時、納品された成果物を独自に編み出した方法で内容チェックを行っていました。
私がミスを頻繁に発見・指摘するので、ある時、調査会社の担当者から 「どうして、ミスを色々と発見出来るのですか? すごいですね。」 と、変なお褒めの言葉をもらったことがあります。
その時、その担当者にチェック方法のポイントを教えてあげましたが、その後、改善・進歩の様子は見られなかったです。
その理由は、多分、’チェック作業の重要性を認識していなかった’ か ’忙し過ぎてチェック作業に取り組む時間がなかった’のいずれかだと思います。
しかし、それ以前に、その調査会社自体がミスの防止に真剣に取組む姿勢がなかったからだと思います。 つまり、経営幹部の無関心が、その社員たちにも蔓延していたのでしょう。
|
◆ JR東海の初歩的ミス! - 作業確認用の <チェックシート> の不備 ◆
単純な 「人為的ミス」 が招いた停電事故!
話は変わりますが、2010年1月29日に東海道新幹線が停電で3時間半も止まり、出張中の会社員や旅行者など15万人に影響が出ました。 利用者の多い金曜日のダイヤを大混乱に陥れたその停電事故は、事故の2日前にパンタグラフの部品交換をした時、作業員がボルトを付け忘れたという単純な人為ミスが原因でした。
部品交換作業は中堅(経験10年)と若手(同3年)の社員2名で行われ、確認役はベテラン社員(同30年)だったそうです。 事故後の聞き取り調査で
「自分たちはしっかりやった」 とのこと。 しかし、同時に交換作業を行った6号車のパンタグラフにはついていた’確認マーク’が、事故原因となった12号車にはついておらず、ボルトの付け忘れであることがはっきりしたそうです。 まさに、「初歩的ミス」の典型です。
人間は誰でもミスをするのに、十分なチェックシステムがなかった!
JR東海は 「普段から人為ミス防止に向けて対策や教育をとっているが、機能しなかった」 と釈明しました。 しかし、作業が済んだかどうかを点検表に記入するとか、残ったボルトの数を確認するといったチェック作業は行わなかったそうです。
ここでの問題点は、人間は誰でもミスをするにもかかわらず、ミスを起こさないように幾重にもチェックをして、未然にトラブルを防ぐ仕組みが抜け落ちていたことです。
この新幹線の停電事故で知ったことの中で、私が一番驚いたことは <チェックシート> が準備されていなかったことです。 このチェックシートがいかに重要なものであるかは、次のような理由からです。
● 人間は誰でも勘違いやミスを起こすので、そのトラブルを未然に防ぐために
は、チェックシートに基づいた確認作業が必須である。
● 複数の体制で行う作業は、「XX がやってくれるだろう (やっただろう)」という
依頼心や気の緩みが生じやすいので、このチェックシートを通じて、念のた
めの確認が必要となる。
上述のケースの場合、若手・中堅が作成したチェックシートを見ながら、確認
役が再チェックを行うべきだった。
● チェックシートに作業項目や点検項目を記入していけば、仕事に対する責任
感や緊張感は増していく上、当然、作業忘れや点検忘れといった単純ミスは
防止できる。
● このような点検作業には、毎日、かなりの人が同じ作業に従事しているはずだ。
チェックシートが準備されていれば、全員が同一項目の作業を漏れなく実施で
き、また、気の緩みや惰性による作業も防止できる。
以上は、JR東海で起きた単純な人為ミスについての話ですが、調査においても人命にかかわることではないと言えども、ミスの防止のためには、真剣に取り組まなければいけない問題です。
|
◆ 調査は <チェック作業の専従部署> と <チェックシート> が必須! ◆
調査会社でもクライアントの信用を失うようなミスを防止するためには、やはりチェックシステムを確立することが重要です。
それは <チェック作業の専従部署の設立> と <チェックシートの作成> です。
チェック作業には、専従部署と担当者の「適性」や「能力」が求められる!
チェック作業は、本来は各調査プロジェクトの内容に詳しい調査企画部(営業部)の担当者が行うべきです。 しかし、現実的には、諸事に忙殺されていることと、ある種の適性が求められるため誰でもいいという訳ではありません。
そのような理由から、この作業には次のふたつの要件が求められます。
① チェック作業は 「集中力」 や 「注意力」 が求められるため、他の仕事と並行しながら片手間に行うことは出来ません。
そのため、このチェック作業を専従で担当する品質管理グループが必要です。
② このグループの実務担当者には、次のような「適性」や「能力」が必須です。
◇ 正確性を重視する
◇ 整合性を重視する
◇ 表示や表記の統一性を重視する
◇ 数字の重要性を理解している
◇ 几帳面な仕事をする
◇ 責任感が強い
◇ 調査の重要性を理解している
このグループの責任者には正社員が就くべきですが、実務担当者は上述のような要件を満たす契約社員やフリーター(含む:就業経験のある主婦)で組織化することが可能です。
そして、実務担当者の仕事の質を定期的にチェックし、常に、精鋭を揃えておくことが、作業の効率化と品質の維持・向上につながります。
調査の「チェックシート」は、正確で効率的な作業に役立つ!
全ての実務担当者が統一した作業を行い、且つ、チェックの正確性を高めるためには <チェックシート> が必須です。 それは次のような効果が期待できます。
● チェックシートの項目に従って行えば、短時間で効率良く、且つ、正確に行う
ことができる。
● チェック作業が途中で中断される状況が生じても、どこまで済んだかが分か
るので、チェック漏れが防止できる。
● チェックする内容が100ページある場合、1ページ目から順番にチェックする
ことが効率的とは限らない。
例えば、3、15、43、68、84ページで類似のチェック内容がある場合、そのペ
ージを先にチェックした方が、頭の中で注意を払うポイントが一定して効率が
良くなる。
また、表示・表記上での不統一な部分(ミスの一種)も発見しやすくなる。
● チェックシートに記録していくと、調査企画部(営業部)や集計部の担当者別
にミスの傾向が出るので、その担当者の日頃の仕事において注意すべき点
や改善すべき点が明確になる。
● チェックシートの作業項目や点検項目は、調査票、コンピューター・アウトプッ
ト・テーブル(集計テーブル)、プレゼンテーション資料、最終報告書ごとに内
容が異なるので、チェック作業に変化があり作業を惰性で行うことがない。
☆ クライアントの信頼や信用を得るためには、’初歩的ミス・単純ミスの繰返し’ や ’致命的ミス’ はあってはならないことです。 チェックシステムの完成度が高まれば、調査会社としての評価や業績も高まります。
そして、そのことは正確を旨とする調査会社の基本理念にも結びつくことですから、経費が多少かかっても、ぜひ、実行してもらいたいことです。 ☆
|
|