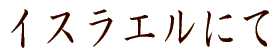 9
9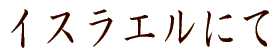 9
9
下りはそれほどきつくはなかった。駐車場に戻り、バスに乗り込む。次は死海を目指す。
死海には2つのビーチがある。一つは金持ち用、もう一つはそれ以外用である。我々が向かうのは、それ以外用である。マサダからはあまり遠くは無い。
駐車場にバスが止まる。もう一台、あの日本人カップルとダマスカス門で会った女の子を乗せたバスも止まった。私はまず、売店に向かった。だが、閉まっている。まだ相当早い時間だからであろう。しかし、隣のキオスクのような売店は開いている。そこに首を突っ込み、おやじに「水着ありますか」と聞いてみる。あいにく、無い、とのことだった。仕方が無い、パンツで入ろうと決心する。駐車場から我々は湖岸に向かう。だが、ダマスカス門で会った女の子は「私はこの前来たから、その辺ブラブラして来る」と言って、左の方に向かう。残りの3人はビーチに向かう。
死海は、小さな波が湖岸を噛んでいる。波打ち際は、塩で真っ白である。多量の塩分を含んでいるためか、泡立ちが水とは思えないほどである。手を死海に入れ、舐めてみる。即座に舌が反応しないのか、特に塩辛さは無い。「ん、味がしないな」と思った瞬間、経験したことの無い味覚が響いてくる。塩辛いではない、辛いのだ。顔が歪み、しかも味がしばらく去らない。「辛えっ!」と、ようやく声が出る。飽和食塩水は、小学生のときに理科の実験で作ったが、味など覚えていない。それほどの衝撃は無かったのかもしれない。だが、この味は忘れられない。マサダから眺めていたとき、カップルの彼女が「水があっていいな」と言っていて、確かにそうかも知れないと思った。だが、この味はその言葉の全てを拒否する。これだけの濃度の塩水が、これほど広範囲に存在すると考えると、やはりここは死の海だ。米西部に死の谷という、豪雪地帯のような塩の平原があるのがあるが、死の海のインパクトは、死の谷を超えると思った。何しろ、豊饒の象徴の水が、この姿なのである。
白人達は早速死海に浮かんでいる。人間なら、普通の水にも十分浮かぶものである。分かってはいるのだが、牛のような白人のおばちゃんが浮いているのを見ると、何だか尋常ではないものを感じる。水は生ぬるい。しばらく死海を眺めていたが、私は衣服を脱ぎ始めた。
裸足で水に近づく。しかし、結晶化した塩がこびり付いている岩の上を裸足で歩くと、かなり痛い。少し切ってしまったほどである。足を踏み入れる。やはり生ぬるい。いきなり膝くらいまで深くなり、そこから徐々に深くなっていく。沖の方に向いていた体を、湖岸の方に向ける。そして、背中から水面に向かって、静かに体を倒す。
プールでも海でも味わったことの無い感覚だ。言ってみれば「浮き過ぎる」のである。湖面で腹ばいになって、顔を出したままで平泳ぎをしてみる。平泳ぎが出来ない。浮きすぎて足が水面から出てしまうのだ。何とか足を沈めようとする。が、沈まずに、体が反り返った状態で湖面をぎこちなく這う。どうしようもないので、また仰向けになってぷかぷか浮かび続ける。空は曇っており、気温はそれ程高くないが、死海の生ぬるさに何だか眠くなってくるような気さえする。このままヨルダンまで流れていってしまえそうである。しかし、あまり長時間浮かんでいると肌がひりひりしてくるらしいので、10分くらいで岸に戻る。浸透圧の影響で体内の水分がかなり出て行ってしまうことから、気がついたらひどい脱水症状にもなってしまいかねない。
岸に上がり、タオルをもってシャワーを浴びる。しかし、中々体の粘つきが取れない。さらに、湖水に髪が触れ、そこが凄まじい硬さを呈している。結局、この髪は宿に戻って洗髪するまで、針金のようであった。
服を着て、死海の沿岸を散策する。残りの時間を、死海を眺めながら過ごす。
時間になり、バスに戻った。しかし、日本人カップルはバスには乗らず、暫く死海を見て回るそうだ。次のエンゲティ国立公園はこのビーチのすぐ近くなので、エンゲティを出発する直前にバスに迎えに来てもらうよう手筈を整えたらしい。
エンゲティ国立公園は、死海に流れ込む小川周辺にあるオアシス地帯。紀元前には人の生活もあったらしいが、現在は動物の棲家としての存在が大きい。すぐ横にはユースホステルがあるが、それ以外に人の住むところは無い。
死海は地峡の底部にある湖ゆえ、周囲は山に囲まれている。海抜下400mで山と言うのは何となく変であるが、それゆえ流れ込む川の殆どが段差を連続して越えて、死海に向かう。つまり、滝が多い。エンゲティは鹿のような野生生物も多く見られるが、魅力は滝である。
ダマスカス門で会った女の子と私は、ゲートをくぐって順路を進んだ。最初は水無川の脇を通っていく。鹿などがいて楽しい。だが、その内谷を登るように順路があって、件の女の子が「マサダルートの再来か」とややうんざりする。だが、マサダほどではなかった。次第に谷が狭くなっていき、崖沿いに歩いていくと、滝が見え始めた。滝壷には白人達が戯れていて何とも気持ちがよさそうだが、私は特に入らない。何しろ、今はパンツをはいていない。先ほどの死海遊泳によって、私の下着はどうにもならないくらいに塩っぽくなってしまっていたからだ。従って、そのときの私は完全なノーパン状態であった。当然そのことは誰にも言っていない。
滝は一つではなく、上流にも連続してあるため、逗留はせずにさらに先を進む。どの滝でも白人達が戯れているが、上流に進むにつれて人は少なくなっていく。やはり、あの巨体では上流まで登るのは難儀なのだろうか。辺りは砂漠とは思えないほどの緑であるが、緑があるのは川沿いだけで、崖の上は全くの禿山である。死海周辺は何かアクセントがあると、すぐにコントラストが目立つ土地である。何しろ、何も無いのだから。
順路最上流に辿り着いた。誰もいない。ここはダビデの滝と呼ばれているらしい。落差もかなりある。滝口は鬱蒼とした緑に覆われ、緑の中から水が流れ落ちている。さらに、滝口周囲の緑の枝葉からも糸のように水が流れ落ち、まあなんと言うか、非常に美しい。台湾の知本温泉で見たような滝である。乾燥帯なのに、亜熱帯のような滝がある。私とダマスカス門で会った女の子は、しばらく無言で滝を見上げていたが、ふいに私が「写真撮ろうか?」と聞く。今までのルートでもそうだったのだが、この風景は、と言うところで写真を撮るように頼まれていたからだ。女の子はニッと笑って、カメラを私に渡す。滝に近すぎて滝全体が入らないが、まあいいやとシャッターを押す。
エンゲティのゲートまで下りたが、まだかなり時間があったので、死海の沿岸まで歩く。その付近は死海沿岸に遊歩道が整備されている。しかし、誰もいない。私たちは遊歩道のベンチに座り、だらだらと話して過ごす。そこで聞いた話。
この女の子は大学2年生で、今回が初めての一人旅だと言う。学校は慶應の法学部だと言う。「え、慶應なの?慶應の女の子がこんなところを一人旅するなんて、かなり意外な感じだね」と言う。それは確かにそうで、付き合いのある友人にもこんなことをする子は一人もいないそうだ。以前に数度、友達何人かとヨーロッパ旅行などをして来たが、前回の旅行で、「今度は一人旅をやってみよう」と思ったらしい。女の子の一人旅はやはり女の子にとっては馴染みが無いらしく、友達は全員少し驚いていたそうだ。しかも行き先がイスラエルと言うわけで、何でそんな訳の分からない国に行くのか、親ですら合点がいかなかったらしい。
自分でも、正直かなり不安を感じていたらしいが、着いてみると案外そうでもなく、また英語がかなり通じるのが良い誤算で、殆ど苦労を感じずに旅行を楽しんでいるらしい。確かにこの子は英語が上手く、また臆せず白人などにも話し掛けることから、旅行を楽しむ資質が備わっていると私も感じる。この子の辿ってきたルートは、私と比較的同じである。違う点は私が地中海のアッコを訪れたのに対し、彼女はゴラン高原を訪れている。ゴラン高原は危険と言う印象があるが、観光客が行けるゴランは自然の豊かな大地である。また、ガリラヤがあんなに豊かだとは思わなかっただとか、セントピーターズフィッシュが大味だったとか、何だか悉く意見が一致する。ガリラヤはともすると、日本人にはあまり面白くないところかもしれない。だが、この女の子はそんな地味な土地に対して、純粋に好意を寄せている。これはいい精神状態だ。この女の子はまた、テルアビブにいるときに夕陽がきれいで海岸に佇んでいると、地元の男が寄って来て、色々誘うらしい。日本人の女の子は海外では人気がある。金を持っているし騙されやすいし、また肌がきれいだから狙われるのだ。「私は夕陽が見たいのに、本当にしつこかった。全く『誰でもいいのか』って感じで腹が立つ」と言う。何だかぼんやりしている感じの子であったが、芯はしっかりしているらしい。まあこういう子なら、海外一人旅でも大体大丈夫だろうなと、私自身の経験から言っても思う。
何しろ、積極的に楽しむ姿勢は大切である。何事にも「つまらない」と言う人間は、大抵本人が楽しもうと言う姿勢が欠落していることが原因であったりするからだ。海外旅行はどこへ行っても楽しいと言うわけではない。初心者のうちは何事も新鮮で楽しいが、旅行経験を重ねるごとに、新しいことに対する抗体が出来てしまい、あまり楽しくないななどと思ってしまう。そうなってくると、自分で楽しもうとする姿勢が無いと、全くつまらない旅行になってしまいがちだ。これが分かるのは、何度か旅行を通じてであるが、この子は初めての海外旅行でそれを無意識に分かっている。日本人にしては珍しいなと思った。案外、女の子はそうなのかもしれない。
クラクションが鳴る。振り向くと、死海から戻ってきた先ほどの日本人カップルをバスが乗せている。そろそろ出発時間のようなので、駐車場に戻る。我々はまたバスに乗り込み、今度はジェリコを目指す。
このツアーは、これまでで殆ど終わりと言っても過言では無い。後はおまけ程度にまわるだけだ。実際、クムランにしてもジェリコにしても、車の中から降りて「5分間のphoto time」しか与えられない。ティベリアで会ったニュージーランド人は、「ジェリコは今ひとつだった」と言っていたが、これはこのようなおまけ的な立ち寄り方しかしなかったからだろう。ただ、昼食はジェリコの食堂で取ることになっている。
クムランを抜けて、ジェリコの街に入ってきた。車は食堂の前に止まり、そこで飯となる。食費はツアー料金90シュケルには入っていない。勝手にここで食べるのだ。しかし、ここ以外に食堂は見当たらない。日本人カップルの2人は、事前にパンなどを買ってきていたので、外で適当に取ると言ってどこかへ行ってしまった。
外に旗が翻っている。イスラエル国旗のデビットスターではない。あれはパレスチナの旗だ。ジェリコがパレスチナ解放機構統治下であることを感じさせる。そう言えば、車のナンバーも違うし、町全体も渇いた感じがする。イスラエルは予想より豊かだと思っていたが、ここはあまりそれが感じられない。
その後は、ずっとバスに乗りながらとなる。朝も早かったし、何だか疲れてきた。所々でバスが止まり、そのたびに5分間の写真タイムになるが、旅行でカメラを携行する習慣の無い私にとって、この時間はその景色を漫然と眺めるだけである。特に面白くもないが、別につまらなくも無い。降りるたびに、他の旅行者とくだらない話をしたりする。
凄まじい山道に入った。どこに向かうのかは分からない。カーブのたびにクラクションを鳴らすが、それはカーブの見通しが悪いのと、道幅が狭いので衝突を防ぐためであろう。かなり登ったであろうが、駐車スペースがあってそこに止まる。ここから有名なワジ(水無川; 大水のときだけ水が流れる)の谷と、その谷にあるギリシャ正教の聖ジョージ修道院が眺められるらしい。写真タイムは10分。私はバスを降り、修道院が見渡せる地点に立つ。
目の前には、今回のイスラエル旅行、いや、いままで見てきた中で最も口をつぐませる景色が広がっている。眼前は、ワジによって削られた深い谷である。その切り込みたるや、とてもワジによるものとは思えない。その切り込まれた崖にはめ込まれるように、修道院がある。だが、修道院があっても無くても、その景色がそれ程変わるとも思えない。そして、圧巻なのは、谷の向こうに広がる荒野である。どこまでも続く、なだらかな起伏の連続。この景色は、茶色の雲の上のようである。まるで金縛りにでもあったかのように、私は少し腕を前に出した変な姿勢で、その景色を眺める。この地点に歩み寄った体勢が凍り付いているのだ。大げさと言われるかもしれないが、この硬直具合は30秒ほど直らなかった。こんな景色は見たことが無い。
気がつくと、ダマスカス門で会った女の子がカメラを手にしている。「写真撮ろうか?」と、一々写真タイムで声をかけていたが、今回は忘れていた。「お願いできます?」と言われ、私はファインダーを覗く。当然ながら、フレームに景色が収まる筈が無い。私はこれが嫌なのだ。これが嫌で、カメラを携行しないのだ。思った通りに景色が収まらない。この景色を収める最良の方法は、今のところ目と脳に焼き付けることであると、何度目かで実感した。「全然入らないけど、いいかな」と声をかける。
車はエルサレムへ向かう。そろそろこのツアーも終わりだ。最後はオリーブ山からエルサレムの景色を眺めると言うおまけがついている。実は昨日行っていたが、別に2回行っても何ら問題は無い。オリーブ山の山頂に着き、エルサレム旧市街を見渡す。雨はすっかり上がっており、陽も差している。目の前は黄金色の岩のドームが望まれ、肩をつき合わせるようにイスラム寺院、キリスト教会、そして民家が詰っている。昨日この景色を見たとき、数年前に大森にある旅行会社の壁に貼ってあった、エルサレムのポスターを見たときを思い出した。あの時、イスラエルなんて遠い国のポスターが貼ってあることに、何だか知らない世界を感じたものだった。東南アジア行きの航空券予約をしたと思うのだが、あのエルサレムのポスターは、完全に異国という印象を私に与えていた。行く筈の無い国として。それが今、目の前に広がっているのを見て「ああ、エルサレムに来たんだな」と、昨日思った。今日はさすがに思わなかったが、ここから見るエルサレムは、やはり何かの力を持っているような気がする。
車に乗り込み、ダマスカス門へ向かう。だが、ダマスカス門に着く前に、解散となった。日本人カップルと、今朝方ダマスカス門で会った女の子を乗せたバスは見当たらない。そう言えば、3人の名前も聞かなかったなと気がつく。スタンドで新聞を買い、ローマ法王の記事を見ながら、ダマスカス門をくぐった。