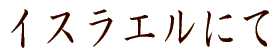 10
10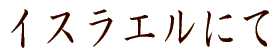 10
10
翌朝。
疲れは取れた。特に体も痛くはない。逆にぐっすり眠ったせいか、今までの旅の疲れも完全に落ちたような体の軽さである。明朝イスラエルを発つ私にとって、今日が事実上最後のイスラエルである。私が今並んでいる列は、岩のドームに向かう列である。昨日ダマスカス門で会った女の子に、「絶対行ったほうがいい」と言われていたから、こうして並んでいる訳である。比較的朝早くなので、あまり長い行列ではなく、またカメラを持ち歩かない私には、何も問題はなく入れる門である。私がカメラを持たないもう一つの理由が、これである。
岩のドームは、あの子が薦めるように確かに素晴らしかった。だが、どうもピンと来ない自分になっているような気がする。昨日もそうだった。マサダツアーから帰ってきて、私は少し街を歩いた。しかし、最早キリスト教会にしても他の宗教施設にしても、何らかの感動をも覚えなくなっている。回教開祖モハメッドの昇天したと言う伝説の残る、岩のドーム内の巨大な岩を目前にしてみても、ムスリムではない私には何の関係も覚えず、普通ならもっと滞在するであろうこの「観光の超目玉」を、足早に去ってしまった。
相変わらず、キリスト教会の周辺には、欧米からの巡礼ツアー客でごった返している。2000年という節目を迎え、このようなツアーは異様な盛り上がりを見せているのだろう。門外漢にとって、これほど虚しい景色は無い。全く分かち合う材料が無いのである。
聖地エルサレム。この聖地に来て私は、世界のどの国にいるよりも、自分はキリスト教と関係が無いと自覚をさせられた。ある意味、これは収穫であったかもしれない。イエスを追おうとして、結局何も追っていないことを自覚させられた。最後のこの日、私はどうしていいのか分からなかった。
同室だった日本人が、ベツレヘムが良かったと言っていたを思い出し、ベツレヘムに向かおうと思った。イエス生誕の伝説の残る街である。東方の三博士が、星を目指して向かったベツレヘム。幼稚園の園児劇で、私が演じたのは東方の三博士の一人だった。東方の三博士が、どのような役割があるのか、当時は全く興味が無かった。私が興味があったのは、同級生がまとっていたローマ兵士の銀色の武具である。私はあれがやりたかった。そんなことを思い出しながら、私はバスターミナルへ向かった。だが、バスターミナルまで行ってみてやはり止めた。面倒臭くなってしまったからだった。その後、ホロコースト博物館にも行こうかと思ったが、これも面倒臭くてやめてしまった。ぼんやりと歩いているのだが、時間があまり経たない。
鶏鳴教会に辿り着いてしまった。かつてペトロがイエスを裏切った場所に建っている教会だ。最後の晩餐だったかで、イエスはペトロに「お前は鶏が鳴く前に、三度私を知らないと言うだろう」と言われ、その通り「イエスなんか知らない」とピラトの宮殿で女給に対して叫んだ場所。それがここである。興味は失せてはいたものの、他に行く所もなく、また雨なども降って来たので、私は教会に入った。
教会は、これまた小奇麗であった。私は可愛らしい椅子に座って、しばらくやり過ごしていた。中には誰もいない。だが、団体客がぞろぞろと入ってきた。東洋人である。だが、輪郭からして日本人ではないことは一目瞭然であった。彼らは韓国人なのだ。韓国にはキリスト教徒が非常に多い。理由は曖昧だが、宮脇俊三著「韓国鉄道旅行記」に登場しているサムさんによれば、「朝鮮戦争の折、仏教は民衆に何もしてくれなかったが、キリスト教はパンを配ってくれ、それで皆が改宗した」とのことである。実際、どの教会にも日本語版のリーフレットは少なかったが、韓国語のリーフレットは必ずといって良いほど存在した。このイスラエルという国は、案外韓国人旅行者の方が日本人旅行者よりも多いかもしれない。何しろ、私のような目的意識のない旅行者とは違うのだから。
教会の地下に進む階段がある。これはイエス時代の地価牢が残っているという。イエスが監禁された牢かは分からないが、とにかく降りてみる。石組の牢が数部屋残り、その壁には無数の十字架と、人影と思しき染みがついている。この部屋が例の部屋だと言うのだろうか。鞭に打たれ、血を流しながら一晩留め置かれたあの部屋が、ここだと言うのだろうか。だとしたら、この石は少しでも血を吸っているのだろうか。
教会の脇には、みやげ物屋と喫茶店がある。私は喫茶店に行き、コーヒーをすすりながら、「死海のほとり」を読む。物語中には、私と同じように、いや私以上にイエスとの距離に少し悩んでいる、中年の2人の男が佇んでいる。私は物語中の彼らを眺めながら、私と重ね合わせようとしてみる。だが、これすらも出来ない。何故なら、彼らにしても端くれとはいえ、キリスト教徒だからである。キリスト教徒の悩みなど、私と比較などできない代物である。
城壁内に戻る。アルメニア人地区を歩く。アルメニア人のように、全く知名度の低い民族が何故エルサレムの一地域を占めるのかはよく分からないのだが、その中にアルメニア博物館がある。とりあえず入ってみる。
中は完全に普通の、アルメニア博物館だった。エルサレムにあるのに、まるでアルメニアの歴史以外に興味がないといった風情である。だが、これが目的なのかもしれない。何しろ、アルメニアなどという知名度の低い国は、行こうと言う者など少なく、また一生そのアルメニアという国を知らずに生きていくことになる。しかし、仮にも多くの人を集めるエルサレムにこのような資料館を建てておけば、それまでアルメニアを知ることのなかった人々が、バルトロマイによるキリストの布教を知り、早くからキリスト保護に転換したアルメニア人を知り、そして、殆ど知られていない近代のトルコ人によるアルメニア虐殺の歴史を知ることができるだろう。何しろ、私のその一人となったわけであるし。アルメニア博物館は、そのような訳で私にはかなり興味深いスポットであった。中庭は鳩の糞だらけであまり清潔とはいえなかったが。
外へ出てまた暫く歩く。とにかく、何の目的もなく、歩く。そんなことをしているから、やはり疲れてきた。私は少し休もうと思い、スタンドで新聞を買い、ヤッフォ門近くの喫茶店に入った。新聞でも読みながら、少し時間を潰すかと思ったのだ。
喫茶店内は明るく、清潔であった。店員らしいが、全くの普段着を来た男に迎えられる。喫茶店は坂に沿って建っているので、店内も階段状になっている。男に促され、店の階段のてっぺんまで進む。そこがレジになっており、注文をしろと笑顔で言う。どうやら先に会計をするらしい。レジは東洋人である。一瞬日本人かと思ったが、にこやかに英語で話し掛けられる。彼女は韓国人さ、と先ほどの男が言う。私は挨拶を交わし、コーヒーを注文した。その場でコーヒーが注がれ、私はコーヒーを持って、少し広めの席に座った。新聞を広げ、ローマ法王の記事を読む。ローマ法王は、昨日はベツレヘムを訪問したようだ。ベツレヘムはジェリコと同様に、パレスチナ解放機構の統治下に置かれる街である。記事には、ローマ法王がPLOのイスラエル政府との交渉を支持するというコメントが書かれている。何気なく新聞を読みつづける。ふと、先ほどのレジの前を見ると、東洋人で私と同じくらいの年恰好をした青年が入ってきた。入ってきたと言うより、何となく呼ばれたという様子である。先ほど私を案内した普段着を着た男が、私の方に手を向けながら、その東洋人の青年に対して何か話している。青年は私のほうに向かってきて、いきなり日本語で「ご一緒してよろしいですか」と言う。日本人なのだ。私は「ええ、どうぞ」と言う。彼は何やら抱えていた書物を脇に置き、対面に座る。私は新聞を読みたかったが、そうもいかないので新聞を脇に置き、コーヒーをすする。「この店に日本人の方が来ると、いつも呼ばれるんですよ。日本人と話せと言われて。だからこうして来た訳です。」と、来た理由を説明される。私はそうなんですかと応ずる。
彼との会話は、私には最も印象的な会話となった。会話は閉店間際まで続くのである...