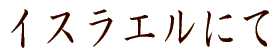 8
8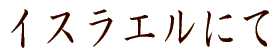 8
8
誰もが眠っているだろうと思ったのだが、案外起きている人間もいる。夜通し飲んだのか、それとも私と一緒に参加するメンバーのうちの一人かもしれない。私は身支度を整えて、そしてかなり厚着をして部屋を出た。フロントには最初の日にいた国籍不明の女ではない、白人の男が座っている。ここにどの程度働いているのかは分からないだろうが、私がこんな時間に起きて来たのは当然驚いていない。この宿でこの時間に起きる人間は、比較的多いであろう。午前3時25分、私は宿を出た。
昨夜は雨が相当降ったが、今は幸い止んでいる。ただ霧が物凄く、エルサレムの路地ですら霞んでいる。幻想的といえば幻想的であるが、不気味と言えば不気味である。何しろ、私はアラブ人街の「玄関口」とも言える、ダマスカス門に向かっているからだ。ダマスカス門の周囲には、当然人影は見えない。ただし、リュックを背負った白人や私がダマスカス門に向かって歩く以外は。
午前3時30分、ダマスカス門まで来る。そこに、数人の人の集まりがある。私は近づいて、カウボーイハットを被った米国人らしき人間に話し掛ける。「マサダツアーに行くのか?」
tabascoという宿に泊まっていることは、この前に述べた。ガリラヤの安宿の泊まっているとき、同室だったニュージーランド人若夫婦に勧められたのだが、彼らのアピールポイントのうちの一つが、この「マサダツアー」だったのだ。朝3時半にダマスカス門集合で、マサダ砦に行ってご来光を眺め、その後は麓の死海だとかエンゲティ国立公園、さらには死海文書の発見されたクムランだとかジェリコなどを回り、午後3時くらいにエルサレムに戻るというツアーらしい。自分でパレスチナ解放機構統治下の一帯を回るのは骨が折れると考えていたので、ここはツアーに参加した方がいいだろうと思っていた私には、正に渡りに船というニュージーランド人若夫婦の情報提供だった。
昨日エルサレムに着いた時点で、フロントで申し込みはしておいた。国籍不明のバンダナ女に丁寧に説明を受けたので、取りあえずのアウトラインは分かっている。私はここで、このツアーで運んでくれるバスを待てばよいのである。それにしても、今日は寒い。
「日本人ですか?」と話しかけられる。振り向くと、そこには小柄な日本人の女の子がいる。「ええまあ」と答える。エルサレムに来て、初めて会う日本人ではない。昨夜も同室の日本人と夕飯を食いに行ったからだ。しかし、女の子は初めてだ。友達と一緒ですかと聞くと、一人旅だと言う。ん、珍しいな、と思う。白人の女の子もよく旅行をするが、大体男と一緒だったり、または友達2人組というパターンが多い。特にカナダ人の女の子は、2人旅をよくしている。日本人の女の子で、こんなフロンティアな旅をしている人もいるが、そもそもあまりいないし、しかも一人旅は私は見たことが無い。私が海外旅行を頻繁にしていた数年前は、日本人の女の子一人旅と言うのは、全くイメージには無かったことである。というわけで、少し面食らった。tabascoに泊まっているのかと思ったのだが、ホスピスと呼ばれるキリスト教会が経営しているところに泊まっているそうだ。このツアーには、別途に安宿のフロントで申し込んだらしい。
バスは中々来なく「寒うー」を連発していたのだが、午前4時過ぎにようやく来た。バスと言うより、大型のワゴンと言う感じであったが、中は相当ゆったりしている。ただ、このバスはtabascoで予約した者のみが乗るらしく、例の女の子は乗らなかった。ただ、この女の子とはツアーの最後まで一緒のルートを辿ることになる。
遅れを取り戻すためか、ベンツワゴンは120km/hで飛ばす。濃霧の暗闇だと凄まじいスピードに感じるが、ドライバーの技量はよく、また車の性能もかなり良いらしく、全く快適である。さすがベンツと感心する。車内にいるのは私以外が全員白人である。国籍は分からない。車はどんどんと進むが、だんだん霧は晴れてきた。さらに進むと、かなり広い領域に渡る水面らしきものが眼前に迫ってくる。道沿いを見ると、すでに砂漠である。こんな凄まじい砂漠に、あれだけの湖面が存在する筈は無い______死海を除いては。
車は死海沿いを猛スピードで走り続ける。左手には死海が広がり、右手には黒い岩山が聳え立っている。真っ暗闇であった外も、やや明るくなってきている。御来光に間に合うだろうかと、不安になってきたとき、ゴンドラのケーブルが見えてきた。バスは右折し、ゴンドラ駅前の駐車場に泊まる。車内灯が点され、ドライバーが我々の方に顔を向ける。何人かはやはり分からない。その男が、やや甲高い声で、バスは7時半に出発するから、7時半までに帰ってきてくれと説明する。このツアーは、ガイドがつかない。ドライバーは、それぞれの観光スポットに客を連れて行くだけで、それ以外の関わりは殆ど持たないのだ。物足りないと感じる人もいるかもしれないが、この車に乗っている我々のような客にとっては、非常に好都合なツアーである。
バスを降り、登山口に向かう。場所はドライバーから教えられている。まだ暗いので足元がおぼつかないが、注意しながら砂地を進む。登山口についた。しかし、まだフェンスが閉まっている。ツアー参加者が足止めを食らう。フェンスを越えて勝手に登山ルートに入る旅行者もいたが、私は暫く待つ。その内、さきほどダマスカス門で会った女の子もやって来る。「何だか開いてないんだよね」、と伝える。周りは白人だらけで、少しざわつき始める。こういうときの白人の動きは速い。誰かが「呼びに行ってくる」と行ってその場を離れる。呼びにって誰を?と言う感じだが、我々は待つのみである。気がつくと周囲は相当数の白人旅行者が詰め掛けている。恐らく、複数のツアーがこの時間にやってきているのだろう。さらに注意を周りに向けると、東洋人のカップルがいる。こんなところを旅行する若い東洋人旅行者は、日本人以外にはありえなく、そしてやはり日本人であった。私とダマスカス門であった女の子は、彼らの近くにより挨拶を交わす。
その内、門番らしきおっさんがトラクターでやってきて、チケット売り場を開ける。私達は入山料の学生料金15シュケルを払い、マサダ砦に向けて出発する。
マサダはアラブ語で要塞などの意味を取る。従って、「マサダ砦」などと言うのは、二重になってしまい相応しくない。マサダはヘロデ王(紀元前1世紀)の避寒地として造営された「冬の宮殿」跡である。しかし、「宮殿」としてのマサダより、マサダは「要塞」としての歴史の方が重い。紀元70年ユダヤは当時の統治者であったローマに対し、大規模な独立闘争を起こす。結局鎮圧されるものの、最後まで抵抗を続けたユダヤが立て篭もったのが、このマサダだったのだ。マサダの陥落、それがユダヤの闘争の最期でもあった。つまり、この地はユダヤにとっては、独立に向けたユダヤの精神的象徴と言っても過言でない存在となっているのだ。
マサダは3年もった。理由は、この要塞が山の頂上に存在するからである。地質上の問題かもしれないが、この山は非常に切り立っているが、頂上は広々とした平地が広がっている。南米のギアナ高地のような感じである。従って、守るには都合がよく、攻めるには非常に難儀する、まさに天然の要塞と言うべき地形をしている。ローマが攻めあぐねたこの砦は、現在はゴンドラが頂上付近まで開通している。そして、登山道も一応整備されている。今日は徒歩による頂上へのアプローチである。何しろ、ゴンドラはまだ動いてはいない。
道は思った程でもなかった。だが、やはり女の子には辛いらしく、何度も立ち止まる。日本人カップルの男の方は、額に汗を浮かべ、やや息が上がる程度であるが、彼女にしてもダマスカス門であった女の子にしても、今にも挫折しそうな駄目さ加減である。どうやらこの登山ルートは、男女の力の境界線上にあるレベルのようだ。我々男2人は女の子のペースに合わせるため、ややゆっくり登る。
そうは言っても辛くなってきたというとき、ようやく頂上付近に達した。あともう少し、あともう少し、などと言いながら、ようやく頂上に到達。すでにかなり明るくなっていたが、どうも日の出には間に合いそうだ。だだっ広い頂上について、水を飲み、息を大きく吐く。
死海の方を見る。鮮やかとしか言いようの無い青色だ。周囲が黄土色なので、余計に際立つ。遠くにはヨルダンの山々が望まれる。ああ、登ってきた甲斐があったと思う。これで御来光が花を添えるのである。
曇で全く見えなかった。
ダマスカス門であった女の子は、実はマサダは二回目だと言う。一昨日に訪れたそうだ。しかし、朝のマサダが見たくて、今日早起きをしてきたと言っていた。全くお気の毒であるが、それでもわざわざ登ってきた甲斐があったのか、やっぱり来て良かったなどと言っている。....前向きだな。
我々はそれぞれバラバラになり、好き勝手に見て回る。マサダはローマに陥落された後、ほぼ廃墟となったらしく、伝説のみが残ると言う地であったそうだが、そのおかげで殆ど当時の面影を残している。私が感心するのは、アーチ構造の普及具合である。石積みだから出てくる発想なのかもしれないが、至る所でアーチが残っている。もう1900年以上、この形を保っているのである。また、貯蔵施設や貯水システムは、噂に聞いたとおりで、貯水施設は、少ない雨水を貯める構造になっており、石で積まれた樋が貯水施設に通じるようになっている。現在は空であるが、当時のシステムが完全に残っている訳ではないからであろう。
死海と反対側に回ってみる。そこから眼下を見下ろすと、明らかに周囲の岩質と異なるスロープ状の構造が見られる。周囲は岩なのに、そこだけが石や砂で出来ているのだ。これはローマの侵入路である。この侵入路をローマは積み重ね、マサダに向かったのである。この侵入路を積み重ねたのは、ローマの捕虜となったユダヤである。ユダヤがローマを通すために、この道を作ったのである。ユダヤが建設すれば、頂上のユダヤはこれに攻撃を加えられないという判断のもとである。
マサダは、現在でもユダヤの象徴的な地であるが、私にはこの坂の矛盾をユダヤがどう理解するのかが気になる。この坂を作るのに、相当の労力と材が使われている。それは見れば分かる。マサダ自体もスケールが大きいが、この坂のスケールも大きい。矛盾のスケールも大きい。坂の右には、ローマの陣地跡が残っているが、この矛盾を眺めていたローマは、何を思っていたのか。何も思っていなかったのか。早く出来ねえかな。とっとと攻めて、早く帰りたいな。そんな感じだろうか。
時間が近づいてきた。下山口に向かう。向こうから、例のカップルが2人で戻ってくる。2人と合流して、暫くまた死海を眺める。カップルの女の方が言う。
「ここにおった人たち、死海を眺めて『ああ、いいな、あそこあんなに水があるで』とか言ってたんちゃうか」
死海の水はとても飲めたものではないが、あの青を見たらそう思うかもしれない。