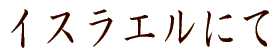 6
6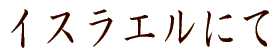 6
6
目覚めると既に外は明るく、また天候も良好であることが分かる。同室のニュージーランド人の若夫婦はまだ眠っている。今朝も起こさないように、静かに準備を整えるが、部屋を出るとき、夫の方が目を覚ます。会釈をして部屋を出る。
バスターミナルまでは歩いていく。来たときは車で送ってもらったが、バスターミナルまでは実は遠くなく、また道も覚えているので苦は無い。それに、ティベリアの朝は歩いていてすがすがしい。朝日を浴びたガリラヤ湖も美しい。
バスターミナルに着いて、エルサレムまでの券を買う。朝食として、売店でパンを買う。イスラエルに来てから当地のパンをよく食べるが、ここのパンはうまい。パンは現在世界のどこにでもあるが、国ごとによってかなり違っている点が面白いところだ。コンビニの菓子パンの種類は、日本以上の国は無い。種類も案外豊富なほうではないか。そしてここイスラエルは、外のパン生地に何らかの調理をしているケースが多い。中にも何かが入っているが、甘いものが殆どだ。しかし、それが甘ったるいという程度ではない。
ここでも軍人が多いが、典型的なユダヤ人の姿も目立つ。典型的なユダヤ人とは、黒い帽子に黒い服を身に付け、髭を伸ばして、さらにもみ上げを伸ばして、その伸ばしたもみあげにカールを巻くという出で立ちをした者たちだ。実はこれまで、このような格好は見てこなかった。ユダヤ人といえば、軍服と欧州風(つまり、普通の西側諸国民)の格好をしている人たちばかりだった。このような格好を見かけたのは、数年前に訪れたニューヨークのユダヤ人街近くである。ああ、エルサレムへ行くんだな、という感触が高まってくる。
バスに乗り込み、ティベリアを後にする。しばらくはガリラヤ湖畔を走るが、その後は畑と緑の間を走っていく。相変わらず、豊かな情景である。そして、西側には山々が見える。今このバスは、ヨルダン川が底部を流れる広い谷を走っている。ヨルダン川はヨルダンとの国境であるので、あの山々はヨルダン領である。川一つ隔てたら違う国、というのは、島国育ちの私からすると今でもうまいこと感触が掴めないことである。そのヨルダンの山々を西に眺めつつ、黄色い花で覆われた大地をバスは進む。エルサレムまでの所要時間は3時間ほどである。途中でベトシェアンにて休憩停車を取る。ベトシェアンは6千年前に出来た街で遺跡もあるらしいが、私はトイレに立ちもしなかった。15分ほどの休憩の後、再びバスは出発する。また暫く草原の上を走るが、単調な景色のせいか眠くなってきた。というわけで、それから小一時間ほど眠りに落ちる。
目を覚まし、車窓に目を向ける。イスラエルと言うのは、予想より豊かな大地を持っている国だと思っていた私は、ここで振り出しに戻ると言うか、その振り出しをも越えて、さらに余計に戻らされたような気になる。驚く。何と言うことだ。どうなってしまったのだ。目をつぶってから1時間、距離はそれ程無い筈だ。それだというのに、こんなにも景色は変わるのか。あの豊かな草木は全く姿を消し、荒々しい黄土色の大地がどこまでも続いている。地獄を見たことは無いが、ひょっとしたら地獄とはこんなではないかという気すらする。そこにいるだけで責めを負っているような気がする大地だ。水や血を全く感知できない大地。
しばらく砂漠に目を奪われていたが、その内少しずつ緑が見え始め、また建物も山の上に見えてくる。家の密度は増し、斜面いっぱいに建物が覆われていく。民家以外の建物を増え始める。そして遠くには、あの岩のドームも見える。ティベリアを出て3時間、首都エルサレムに到着した。
エルサレムはイスラエル国内に存在する他の「古くから存在する都市」同様、城壁に囲まれた旧市街と、ユダヤ人たちが入植した新市街に分かれる。バスターミナルは新市街に位置するが、旧市街までは市内バスでさらに15分ほどの距離を行かねばならない。私がエルサレムで過ごす宿は、ティベリアで会ったニュージーランド人の若夫婦が勧めてくれた"tabasco"というゲストハウスだ。欧米の若い旅行者達には有名な宿らしいが、この宿は旧市街内にある。私はバスターミナル前からさらに市内バスに乗り込み、旧市街を目指す。
エルサレム新市街は、全く以って欧州内の街と相違ない。通りの造りなどは、欧州のそれとよく似ている。数千年の歴史を持つ街というより、20世紀の街と言う印象しかない。だが十数分走ると、今まで見た何物より、いかめしい城壁が迫ってくる。エルサレム城壁ヤッフォ門前で下車し、ヤッフォ門からエルサレム入城。いよいよ、エルサレムに入ってきた。
アッコでは門をくぐると雰囲気が一変したが、エルサレムはヤッフォ門をくぐっただけではそれほど変化は無い。ヤッフォ門は現在、エルサレム城壁の玄関口的な場所であるため、小奇麗に整備されている。車の進入も可能である。私はまず観光案内所に入って地図を確保し、旧市街に入り込んでいった。まず目指すはtabscoである。あまり雰囲気の変わらなかったヤッフォ門前からは一変して、路地に入るとその雰囲気はアラブに変わる。だが、欧米からの巡礼観光客も多いせいか、アッコほどの濃さは感じない。ただ、とにかく賑わっていることは確かである。そんな中、アッコと同様、いや全くそれ以上だったのは、路地の複雑さである。とにかく、教えられたとおりに歩いているつもりなのだが、全くtabascoに着かない。同じところを何度も何度もぐるぐる回る。もう嫌になってきたというとき、違うアラブに教わった道でようやくtabascoに着く。
tabascoというネーミングはよく分からないが、ドアにデカイtabasco瓶の絵があることから、あのパスタなどにふりかけるタバスコがもとになっているらしい、ということを到着と同時に気付く。ドアを開けると、そこがすぐフロントである(フロントと言うほどの代物かは定かではないが)。フロントにはバンダナを巻いた若い女性がいる。顔立ちからしてイスラエルの人間かは分からない。ゲストハウスの経営者や従業員には色々いて、旅行中の旅行者が臨時雇いでやっていたりするケースや、旅行していてそこにいつくというケースもある。従って、この宿の人間がイスラエルの人間かは分からない。そのイスラエル人だかなんだか分からん女性に、極めて流暢な英語で対応をされる。口調は丁寧ではないが、不機嫌さを感じるものではない。幾晩泊まるかは分からないが、とにかくここで数日を過ごす予定である。
個室にするかドミトリーにするかと問われたが、ドミトリーと即答する。一応卒業旅行であり、金が無いわけでもないのに、個室などとはとても言えない癖がまだまだ抜けない。ドミトリーに通され、ここでいいかと問われる。ドミトリー一室はかなり広く、2段ベッドが8つで16人収容と言う広さである。ベッドを選べと言われ、2段ベッドの下段を選ぶ。大雑把な利用規則みたいな説明を受け、ようやく重い荷物から解放される。時間が昼だったせいか、旅行者達は殆どいない。しかし、向かいのベッドに私が持っているのと同じ、例の黄色い背表紙のガイドブックが置いてある。イスラエル入国以来初めて、日本人と顔を合わすことになりそうだ。
宿を出てどこに行くかを考える。見るべきものは多い。とりあえず、街を歩くことにする。私の泊まるtabascoは、聖墳墓教会のすぐ近くである。聖墳墓教会とは、イエスが磔にされたゴルゴダの丘跡に建てられた教会である。つまり、tabascoはイエス最期の地の傍にある。したがって店も多く、かなりの観光客の往来がある。そこを拠点に、縦横無尽に歩くのだが、路地と言う路地が全く予測のつかない迷路ゆえ、瞬く間に方向感覚を失う。アッコ滞在中もそうであったが、エルサレムはアッコの比ではない。また、城壁内の広さもかなりあり、どこまで行っても城壁に辿り着けないような広さである。また、エルサレム自体が斜面に作られたらしく、西側から東側は全体的に坂になっており、南北は平らな道が続く。坂は城壁外東側のゲデロンの谷まで続き、再びオリーブ山向かって大地が上昇していくという感じだ。また、城壁内は様々な勢力によって地区が分かれている。ムスリム地区、ユダヤ地区、キリスト地区、さらにキリスト地区はアルメニア派などの分派もその地区を持っている。最も外国人にとって危険なのはムスリム地区で、夜は特に危険であるらしい。アラブの男達に囲まれてボコボコにされたというケースも聞く。エルサレム旧市街内の最大勢力は、やはりムスリムであり、旧市街内を歩いていてムスリムの雰囲気以外はあまり感じられなかった。
目的をもたずに歩いていたが、疲れたので城壁から出ることを考える。歩きに歩いて、城壁南東に位置する、糞門から城壁外に出た。糞門とはいささか激しいネーミングだが、その昔エルサレムの排出物がこの門から出されたことがその名の由来だそうだ。遠藤作品に馴染み深い私には、この糞門は愛着があると言うか、見てみたいものの一つだった。だが、この糞門はイエス時代のものではない。イエス時代は現在と城壁の位置が異なり、現在の糞門を出たあたりはまだ城壁内だったのだ。また、現在は城壁のほぼ中心に位置している聖墳墓教会(すなわちゴルゴダの丘)は城壁外であった。今の糞門はそのような訳で、オスマン朝支配下時代のものである。糞門以外でも、現在エルサレム城壁内に残る大部分はオスマン朝のものである。
城壁に沿って歩き、ゲデロンの谷を見下ろす。その先の斜面には、いくつかのキリスト教会が見える。その斜面こそ、オリーブ山の斜面で、ここから見えるのはゲッセマネ跡地である。オリーブの実から油を採る場所であるが、イエスがユダヤに捕らえられたあの場所である。
エルサレム城壁を囲むように進みながら、ゲデロンの谷を越え、ゲッセマネ跡まで辿り着く。この隣には「万国民の教会」とか言う教会が建てられている。全世界のカトリックの献金によって建てられたらしいので、この教会はカトリックのものである。その斜め上には、少しロシア風の建物がある。あれはマグダラのマリア教会で、ロシア正教で信仰の篤いマグダラのマリアの名を冠したロシア正教会である。私はゲッセマネの園跡に入り、万国民の教会の前にも行く。入口は観光客でごった返しており、とても中には入れない。
ここであることを思い出した。帰りの航空券の予約再確認をしなければならない。いわゆるreconfirmであるが、私の乗ってきたトルコ航空はreconfirm必須と言われている。72時間前までには再確認をしなければならないのだが、72時間前はとっくに過ぎている。トルコ航空はreconfirmが無いと、容赦なくほかの客を入れてしまうということを聞いたことがある。この時点で、ゲッセマネでイエスの苦悩を思い起こすゆとりなど無く、公衆電話に走る。
イスラエルの公衆電話はほとんどカード式である。カードは買っておいた。早速電話をする。だが、全くつながらない。何度電話しても、トルコ航空は話中のようなのだ。いや、話中というより、どうも誰もいないような気がする。とにかく、トルコ航空に十数回と電話をしても、全くつながらない。海外旅行十数回目で初の苦悩....帰れないんじゃないかと気を揉む。暫く歩いて、公衆電話を見つけるたびに電話をするが、やはり全くつながらない。ありえないことであろうが、ひょっとしたら電話番号が間違えているのかもしれない。営業時間外なのかもしれない。飛行機会社の事務所はエルサレムには無いらしいので、これは同業他社に聞くしかないのではないか。そう思い、まずはイスラエルのエルアル航空に電話を入れる。だが、テープ対応であった。仕方が無いので黄色い背表紙のガイドブックを開いて、エジプト航空に電話をする。トルコと同じイスラム教国だから、絶対にトルコ航空の情報もあるだろうと思ったからだ。だが、電話の対応は冷ややかだった。藁をもすがる思いで電話口のお姉さんに「トルコ航空の営業時間を教えてくれ」と聞いたのだが、「知らないわよ」という感じで突き放される。当たり前と言えば当たり前なのだが、ゲッセマネの前で私は途方にくれる。では連絡先を教えてくれというと、それも知らないと言う。考えてみれば、アラブ系の航空会社に乞うのが間違いだったのかもしれないが、その代わりに電話番号案内の番号を教えてもらう。日本の104である。仕方なく、そこにかけて確認をする。そこで得たトルコ航空の電話番号は、私の持つものと全く同じ。そして、再び電話をかける。ツーツーツー....いい加減にしろ。普段なら、最悪帰れなくても大丈夫であるのだが、今回は帰るその日が卒業式である。研究室に愛着以上のものを持っていた私にとって、卒業式を切ることは出来なかった。何としてでも帰らねばならない。だが、数十回目で、ようやく"hello"という声が聞こえた。ハローじゃないよ全く。