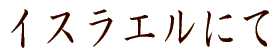 5
5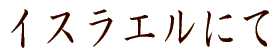 5
5
夕方にはティベリア市内に戻ってきた。ティベリアをこえて、湖畔をさらに南に向かうと温泉があるらしい。だが、湯治をした後で自転車で帰ってくる途中に、体が冷え切ったら全く意味が無いと思い、これで自転車に乗るのはやめて宿に一旦戻った。
フロントで自転車を返す旨を伝え、鍵を貰おうとすると、すでに同室の旅行者が帰ってきていると言う。普通のドミトリーのシステムは、最後に部屋を出る人が、その部屋の鍵をかけてフロントに渡して外出し、一番最初に帰ってきた人が、フロントで鍵をもらって部屋を開けると言うものになっている。ここもそうなっており、一応帰ってくるときは必ずフロントで確認する。ここで鍵が無いので、私が最初に帰ってきたものではないということになる。部屋に戻る。
部屋に戻ると、確かに一人がベッドで眠っており、もう一人はシャワーを浴びている音がする。寝ているのは、金髪の女だ。起こさないように音を立てなかったつもりだったが、気配を察して女が起きた。しかも、いきなりの東洋人に驚いたのか、ハッとして息を飲みながら起き上がった。このような反応には慣れている。"Hi"と私が声をかけて、「警戒することは無い」みたいな表情をすることで、向こうの肩の力が抜けるのがパターンだ。どうも東洋人は彼ら白人にとって、蛮人とまでは行かないかもしれないが、やや毛色の違う(確かに金と黒は違う)人種としてみる傾向がまだまだ強い。これは私一人の力ではどうすることも出来ないので、このような反応を受けるのは仕方ないものとして受け止めている。やや不愉快ではあるが。
夕飯を食べるために、部屋を再び出た。もう一人の旅行者は、まだシャワーを浴びていた。
ティベリアをふらつくのは、着いて以来この瞬間が初めてであったが、前日滞在したアッコとは雰囲気が若干異なっている。アッコは旧市街に滞在したので、アラブ色が非常に強かったのだが、ここはユダヤの色が濃いらしく、街自体が小奇麗である。しばらく街を歩き、夕闇のガリラヤ湖畔などを歩いて過ごす。イスラエルの緯度は、日本の鹿児島付近と同様であるが、気候は地域によってマチマチで、ガリラヤは昼はこの時期Tシャツで過ごせるほどである。ただ、夜はやや冷える。ところどころに十字軍時代の城壁などが残っており、キリスト教会も多い。イスラムの寺院はあまり見なかったが、ユダヤの会堂(シナゴーク)は当然ある。
夕飯に何を食べるかは、すでに決定している。一応ガリラヤ湖に来たのだから、「セントピーターズフィッシュ」を食べてみようと思っている。セントピーターズフィッシュはその名の通り聖ペテロ、つまり先ほど訪れた首位権の教会付近でイエスに見出され、最終的にローマで処刑になった初代ローマ法王のことであるが、この男がこの湖で漁師として生計を立てていた当時からガリラヤに存在していた魚であるとのことでネーミングがされた魚である。ペテロが捕っていた魚だろうから、セントピーターズフィッシュである。勿論、ペテロ時代は違う名だっただろうし、今でもこの名で呼ぶのは外国人だけかもしれない。そもそも、何故かネーミングが英語であるところがおかしい。しかしこのペテロ、地域によって読み方が異なるのはどういうことか。イタリアのサン・ピエトロ寺院、ロシアのザンクトぺテルブルク、そしてこのセントピーターズフィッシュ。欧州の各地で、その国でのアルファベットの読み方で変わってくるのか。そう言えば、georgiaは英語だと「ジョージア」だが、ロシア語だと「グルジア」になるのと同じか。考えてみれば、東アジアでも「金日成」を朝鮮では「キムイルソン」と呼ぶのに対し、日本では「きんにっせい」と読んでいたのとも同じかもしれない。漢字圏ではその国の漢字の読み方にあわせた読み方をする。江沢民も「ジャンズェミン」と「こうたくみん」だし。
話が大幅に逸れた。セントピーターズフィッシュを食べに行く話である。レストランを数件物色したが、結局湖畔のレストランに入ることにした。セントピーターズフィッシュの定食みたいなのとビールを一本頼み、しばらく待つ。店内は閑散としており、客は数組だが外国人の姿は見えないようだった。料理が出てくるまで、しばらく遠藤周作の「死海のほとり」を読む。
この旅行で持ってきた本は、例の「黄色い背表紙のガイドブック」と、この「死海のほとり」。私をイスラエルに誘う最初のきっかけとなった、この本を持っていかずにはいられなかった。この本の主人公は、イエスとイエスに関わった人たち、それから「私」という遠藤自身を模写したと考えられる人物と、「戸田」という大学時代の友人、それから「ねずみ」と渾名を付けられていたポーランド人修道士のコバルスキ...。私は今、ここに描かれている「イエス」と「私」の後を追ってここまで来た、と言っていいかもしれない。だが、旅行前に研究室やバイト先の友人たちから「どうしてイスラエルなんかに行くんだよ」と聞かれたとき、なんだか「イエスを追いに行く」などと言うのは他人からは馬鹿馬鹿しいと取られるような気がして、「遠藤周作のファンなんだよ」と言って出てきたのだ。入国時「何故イスラエルに来た」と入国審査官に聞かれても、当然真実は話さずに「前から来たいと思っていた」などと適当なことを言って茶を濁した。この旅行の目的は、全く誰にも言っていなかった。別に重大な理由でもない、些細な理由であるのだが、羞恥心がそうさせていたと言っていいだろう。
セントピーターズフィッシュが目の前に出てきた。予想よりはるかに大ぶりな魚で、食べきれるか不安であった。しかし、味は淡白過ぎて、あまり美味しいとは思わない。醤油が欲しいが、そんなものは当然ない。イスラエルの料理は、他の中東も同様だと思うが、オリーブオイルがふんだんに利用されており、また肉も羊肉が多い。オリーブオイルも羊肉も私は大丈夫だが、これが駄目な人は中東には来ない方がいいだろう。だが、このセントピーターズフィッシュは、しつこい中東の味と比較して、大味というか何と言うか、期待はずれとはこのことかという印象であった。
レストランを出て、また湖畔を散策する。やはり夜はやや冷える。レストランのすぐ前は、大きなみやげ物センターみたいのが建っており、湖面はあまり見えない。だが、湖面が妙に輝いているのは感じ取れる。瞬間、何かが行われているのではないかと思う。ひょっとして漁火だろうか。しかし、漁火にしては広範囲に輝きすぎている。一体何だと思い、場所をずらして湖面が完全に見られるところまで移動する。
さすがに息を飲む。湖面を輝かせているのは、満月の光であった。月がここまで明るいとは、私は知らなかった。後ろを振り返ると、月明かりでくっきり私の影が出来ている。周囲に何の街灯もないことから、これは月明かりによって出来た影に相違ない。湖畔にはカップル達がいるので、この月を見に来たのかもしれない。湖面で反射する月の光は、少し眩しい程である。この情景をこれ以上説明することは出来ない。いくら説明しても、見た者にしか分からないであろう。
宿に戻ると、先ほどシャワーを浴びていた旅行者もベッドの上に座っていた。金髪の女の連れらしく、こちらは栗色の髪をした男である。挨拶を交わし、彼らが夫婦であることを知った。話を聞くと、彼らはニュージーランド人だが英国で働いていたらしい。しかしこの度会社を辞め、ニュージーランドに帰る途中にイスラエルに寄ったという。オーストラリア人やニュージーランド人がよくやるパターンの、ユーラシア大陸を横断して、シンガポールあたりから故郷に帰るというパターンかもしれない。その時はそこまでは頭が回らなかったものの、あの風体はそうかもしれない。殆どの日本人にとっては想像できないやりかただが、このような話は何度も聞いたことがある。羨ましいかと言われれば、正直に羨ましい。これからヨルダンに抜け、シリア・トルコ・イラン・パキスタン・インドと抜けていくのだろう。途中のミャンマーからタイは国境が開いていないため、陸路は無理だろうが、タイからシンガポールはすぐである。また、トルコから旧ソ連の中央アジアに抜けるというパターンからロシア・モンゴル・中国・ベトナム・ラオス・タイというパターンもある。ロシアに抜けなくても、カザフスタンから中国に入るのも可能だし、パキスタンから中国に入ることも可能だ。中国からはラオスにも抜けられるし、そこからネパールにだって入ることも出来る。私自身、何度となくユーラシアの地図を眺め、脳にこびり付くくらいその地勢関係が鮮明に頭に入っているが、実際に地図を見れば、もっと様々なルートが描けるだろう。
だが、その時に彼らと話したのは、エルサレムの状況である。彼らはすでにエルサレムからここまで来ており、エルサレムの情報をよく知っていた。黄色い背表紙のガイドブックは使えないので、このような旅行者の話を参考にするのが最も手っ取り早く、正確な情報源となる場合も多い。私がまず心配したのは、エルサレムの警備状況である。ヨハネパウロ二世が来るのである。当然警備は厳しくなり、少し影響が出るかと思ったのだ。だが、彼らの話によれば「大したことはないだろう」という観測であった。少なくとも観光客にとって不愉快なことはない筈だと言っていた。後に行って思ったが、確かにこれは当たっていた。また、エルサレム周辺の観光地についても聞くと、「死海は面白かった。これは行った方がいい」というのと、「ジェリコ(世界最古の街とされる)は期待はずれだった」などと言われる。ジェリコは現在、アラファトのパレスチナ解放機構の主権下に置かれている地域で、正確にイスラエルと呼べる地域ではない。所謂「ヨルダン川西岸地区」であり、第二次大戦後でもおいそれと行けない時期があったり無かったりを繰り返した地域である。現在は旅行者でも行けるが、イスラエル政府としてはそこに行く人間をあまりよろしくは見ない。入国時、全く行き先が決まっていなかったので、どこの街に行くかと言われたとき、「決まってないけどエルサレムとかジェリコとか」と言ったら、「何故ジェリコだ?」と、さらに詰問されて難儀したのを思い出した。それを彼らに言うと「そりゃー、いくらでも行くところがあるのに、いきなりジェリコなんて言ったのが悪いんだよ」と笑われた。
色々話をしているうちに、彼らが歴史の話を持ちかけた。どうも男の方は、大学で歴史を専攻していたらしく、私にそんな話を振ってきたのだ。だが、私の答えは明快だった。「色々イスラエル関連の本は読んでから来たけど、この国の歴史は複雑すぎて全く理解が出来なかった」。すると、彼らはそれはもっともだと言う風に、笑いながら頷き「そうだよな、ユダヤが来たりローマが来たり、イスラムが来たりトルコが来たり、最近ですら訳が分からないものな」と答えてきた。
ひとしきり話すと、夜も更けてきた。話を打ち切り、私はシャワーを浴び、その後はすぐにベッドに入った。明日はエルサレム入城である。