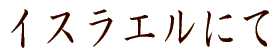 4
4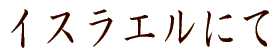 4
4
そののちイエスは、神の国の福音を説きまた伝えながら、町々村々を巡回しつづけられたが、十二弟子もお供をした。また悪霊を追い出され病気をいやされた数名の婦人たち、すなわち、七つの悪霊を追い出してもらったマグダラと呼ばれるマリヤ、ヘロデの家令クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、そのほか多くの婦人たちも一緒にいて、自分たちの持ち物をもって一行に奉仕した。
マグダラは、現在は湖からは少し離れたところに、ミグダルという名前を変えて存在していた。ユダヤの開拓地ゆえ、当時のマグダラとの連続性は無いに等しい。かつてのマグダラは、湖畔にあり、現在でも遺構が残っているという情報を持ってはいたが、特に覗きに行こうとは思わなかった。正確にどこにあるか分からないし、分かっても湖畔からはかなり離れたところまで来ている。見て戻ってきたら、カペナウムまで時間的に行けないような気がしたのだ。カペナウムまではあと9km。起伏を考えると、それほどすぐには着けまい。ミグダルは、ただ通り過ぎることにした。
そこからしばらく行くと、また湖畔に出る。それにしても、この大地の豊かさはどういうことか。黄色い花が咲き乱れているのだが、これが大地を黄色く覆うほど咲いているのだ。自転車をこぎながらも、まだ意外感は拭えなかった。その昔、貧しい漁師が、税に苦しみ、伝染病に苦しんだ土地と聞く。しかし、それは人間だけの話で、この自然とは何の相関性も無かったのかもしれない。マラリアが流行ったほどと聞いたので、現在よりも温暖で湿気があり、つまりもっと自然は豊かであったかもしれない。
起伏の激しさは増す。ペダルをこげばこぐほど、自転車で来るんじゃなかったと後悔する。私の横を、私など簡単に踏み潰せるトラックが何台も追い抜いていく。その度に、暑苦しい排気を浴びながら、それでも前を目指す。ついに、私を完全にへこませるほどの、凄い坂が目の前に現れる。坂の前に自転車を止め、水を飲む。これからどうするかと思う。だが、戻ろうという気は起きない。この坂を登りたいという気も当然起こらないのだが、取り敢えず、再び自転車に跨り、坂を登る。
坂を登りきり、爽快な下り坂を降りたところが三叉路になっている。その右方向を示す標識に、キリスト教会をモチーフにしたマーキングがなされている。三叉路を右に回り、一気に坂を下りおりる。右手に駐車場が見え、観光バスが数台止まっている。売店もあり、周囲には白人がたくさんいた。この教会は何だろうと、標識を見る。「パンと奇跡の教会」であった。ティベリアを出て1時間ほどが経っていたが、ようやく目的地に辿り付いた心地がした。
イエス言ひ給ふ。「パン幾つあるか、往きて見よ」彼ら見ていふ「五つ、また魚二つあり」。イエス凡ての人の組々となりて、青草の上に坐することを命じ給へば、或は百人、あるひは五十人、畝のごとく列びて坐す。かくてイエス五つのパンと二つの魚とを取り、天を仰ぎて祝し、パンをさき、弟子たちに付して人々の前に置かしめ、二つの魚をも人毎に分け給ふ。凡ての人食ひて飽きたれば、パンの餘、魚の残を集めしに、十二の籠に満ちたり。パンを食ひたる男は五千人なりき。
教会の敷地のすぐ外に、売店があった。売っているのはみやげ物が主だが、何故かオレンジや苺などの果物まで売っている。苺は、信じられないほどの大きさである。ガリラヤの豊かさをここでも確かめられる。私は売店でアイスを買い、食べ終えてから教会内に足を踏み入れた。
教会は驚くほど小奇麗である。床はビサンチン時代に作られたモザイクであると、案内書に書いてある。様々な動物が、モザイクに描かれている。有名な二匹の魚も描かれている。その前に、大体人が手で抱えられる籠くらいの大きさの岩が、地中から生えているようにある。この岩で、イエスがパンと魚を増やしたという、伝説の岩である。その岩を、私は懐疑的な目で見つめる。左横は、地面が見えるようなガラス張りになっており、そこには4世紀にこの地に建てられた教会の礎石が見えるようになっている。私は、こちらの方が興味を引いた。
教会は、多くの白人観光客で賑わっている。コンダクターのおばちゃんが案内しているケースも多いが、牧師や神父につれられているケースも多い。彼らは片手に聖書を持ち、牧師や神父は、聖書を開きながら説明をしている。白人達がどこから来たのかは分からないが、その表情は世界各国のツアー客と殆ど変らない。よく批判される「日本人は群れて行動」というのは、実は日本人自身から発せられたものなのではないか。どの国に行ってもツアー客はいるが、日本人観光客だけが異なっていると言う印象を受けたことは無い。誰もが同じように、同じバスで移動し、同じ説明を聞き、同じホテルで泊まり、同じツアー仲間と話す。ここには日本人ツアー客などはいなかったが、日本人ツアー客のいる風景といない風景に、どれほどの違いがあるのか。
教会の敷地内にも売店がある。そこで売られているものは、観光地ならありそうなものばかりである。例えば日本にはどの都市にも、その都市の名前を記した提灯などが売られているが、ここでもisraelなどと書かれた製品が溢れている。黄色い背表紙のガイドブックの使えなさ加減に業を煮やしていた私は、ここで地図を購入した。
話がすむと、シモンに「沖へこぎ出し、網をおろして漁をしてみなさい」といわれた。シモンは答えて言った、「先生、私たちは夜通し働きましたが、何も取れませんでした。しかし、お言葉ですから、網を下ろしてみましょう」。そして、そのとおりにしたらところ、おびただしい魚の群れが入って、網が破れそうになった。そこで、もう一そうの舟にいた仲間に、加勢に来るように合図をしたので、彼らが来て魚を両方の船にいっぱい入れた。そのために、舟が沈みそうになった。これを見てシモン・ペテロは、イエスのひざもとにひれ伏していった、「主よ、私から離れてください。私は罪深い者です」。彼も一緒にいた者たちもみな、取れた魚がおびただしいのに驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブとヨハネも、同様であった。すると、イエスがシモンに言われた、「恐れることは無い。今からあなたは人間をとる漁師になるのだ」。
「パンの奇跡の教会」の隣には、ペテロ首位権の教会がある。湖のほとりに建てられた教会である。相変わらず、牧師や神父につれられた巡礼ツアー客が多い。この教会の庭園は美しいが、教会の建物は地味である。中に入ると、先ほどのパンの奇跡教会とは比較にならないほど、巨大な岩が祭壇にある。イエスが復活した際、弟子に飯を振舞った岩と言う伝説が残る。岩の上には、夥しい数の蝋の後がこびり付き、あまり美しいと言う印象が無い。
見上げると、黄色と白の下地に、なにやらの紋章が描かれている生地が目に入る。バチカンの国旗である。次の日には、バチカンからヨハネパウロが、ここイスラエルの地に巡礼の一環としてやってくるのである。ペテロ主位権の教会は、当然ローマカトリックの所管であるのだろう。ヨハネパウロは、この教会にもやって来ると聞いたような気がした。外に出て、改めてこの教会を見る。大して地味では無いように思うのだが、ペテロを考えると地味に思える。数年前に見た、ローマのサンピエトロ寺院の威容とは、比較にならない地味さ加減である。正確ならば、イエスとペテロが、そこの湖岸で出会ったわけであるが、遠くローマの地でペテロを祭ったサンピエトロ寺院は、何故こうも違うのか。
「ここで漁をしていた男が、2000年後にはローマの派手な墓に眠っているのか」
湖を見ながら妙な感慨を覚える。
いきなり、目の前に黒尽くめの男が現れた。衣装は聖職者のそれで、衣装そのものも真っ黒であるが、顔も手も真っ黒である。黒人の聖職者である。何も言わずに、教会に入って何やらしている。覗いてみたが、観光客に配るチラシを補給しているのだ。補給をし終わると、教会から出てきて、教会の住居の方に向かって歩いていった。私も首位権教会から発とうと思ったので、彼の後を追う形で辞した。門まで行く途中、白人の観光客が、この黒人聖職者に話し掛けている。話題は、白人が黒人にどこから来たのか尋ねるというものだった。黒人はあててみろと言うので、白人がアフリカの知っている国を片っ端から言いまくるという、何やら滑稽な風景が続く。黒人聖職者は、笑いながら"no"を連発し、白人は次から次へと、大声でアフリカの国名を叫びつづける。何をしてんだか。
カペナウムに着いたが、遺構は見なかった。大した理由ではなく、自転車を止めるいいポイントが無かったためだ。そろそろティベリアに帰るかと、道を引き返し始めた。
イエス群集を見て、山にのぼり、座し給へば、弟子たち御許にきたる。イエス口をひらき、教へて言ひたまふ、
幸いなるかな、こころの貧しき者。
天國はその人のものなり。
幸いなるかな、悲しむ者。
その人は慰められん。
幸いなるかな、柔和なる者。
その人は地を嗣がん。
幸いなるかな、義に餓ゑ渇く者。
その人は飽くことを得ん。
幸いなるかな、憐憫ある者。
その人は憐憫を得ん。
幸いなるかな、心の淸き者。
その人は神を見ん。
幸いなるかな、平和ならしむる者。
その人は神の子と稱へられん。
幸いなるかな、義のために責められたる者。
天國はその人のものなり。
我がために、人なんぢらを罵り、また責め、詐りて各様の悪しきことを言ふときは、汝ら幸いなり。喜びよろこべ、天にも汝らの報いは大なり。汝らより前にありし預言者たちをも、斯く責めたりき。
やはり登るべきではなかった。黄色い背表紙のガイドブックには、なだらかな坂と書いてある。なだらかだと?一体、何度カーブを繰り返せば気が済むのか。見上げても、中々山の上の垂訓教会は近づいてこない。あれからすぐに、ティベリアに帰ればよかったのかと、また変な後悔を繰り返している。もうべダルをこぐ気にもならず、道端で水を飲み、自転車を押して登る。道端には牧場があり、牛達が草を食んでいたが、私が通るのを見ると、一斉に草を食むのを止め、私のほうを見ている。十数頭の牛達が微動だにせず、私を見ている。その視線は、ガンを飛ばすような険しいものではなく、なんと言ったらよいのか、とにかくただ見ているのである。私がゆっくり道を進むと、私のほうを「ただ見ながら」首を私のいる方向に回す。十数頭対一人のアイコンタクトが数分続く。
パンの奇跡の教会前から40分をかけて、ようやく山上の垂訓教会に到着した。ここでも、観光バスが数台止まっており、巡礼ツアーの白人達が大勢教会敷地内に入っていく。この教会は、少し豪華だ。敷地も広く、教会の建物も立派である。八角形の建物で、中もきれいである。湖側には庭園があり、そこから見下ろすガリラヤ湖は格別の美しさである。地面は黄色い花で覆われ、その向こうには青い湖面が広がり、さらに向こうには群青色の山々が連なる。あの山の向こうはシリアである。ここまで自転車で登ってきたのは、この中では当然私だけであろうが、バスで上ってきた人間に比べれば充実感が違う。何せ、ここまで40分もかかったのだ。ガリラヤ湖畔は比較的暑く、汗をかなりかいたが、湖から吹いてくる風がなんとも心地よい。しばらくの間、逗留を続ける。
山を降りるのは、5分しかかからなかった。先ほどの牛氏たちと目も合わせられないようなスピードで降りてきたほどである。それにしても、40分と5分...
ティベリアへの帰路、動物の死体が道端に転がっていた。犬が車にはねられたのだろうか。近寄ってみてみると....何だこの生き物は。見たことが無い。丸々とした可愛い奴だが、可哀相にこのアスファルトの上で息絶えている。その横を、猛スピードで車が走り去る。