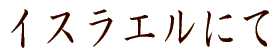 3
3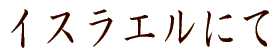 3
3
同室の旅行者の寝息が聞こえる。誰一人として起きていない。起こさないように、静かに出発の準備をする。場所を移動する際、私はいつも同室の誰よりも早く起き、誰にも気付かれないまま宿を出る。移動すると決めたら、とにかく早くその街を出るのが、私の旅先での前進の仕方である。特にイスラム圏の国では、まだ薄暗い中をコーランが鳴り響く街を、ひたひた歩きながらその街を後にするのがスタイルだ。しかし、この日は既に日も昇っており、またコーランも聞こえなかった。というより、イスラエルに来てコーランを耳にした記憶は無い。確かにイスラム寺院は存在しているのに、何故私に聞こえなかったのかは、よく分からない。
バスターミナルについた。今日向かおうとしているのは、ティベリアである。ティベリアとは、ガリラヤ湖畔の観光中心都市で、かつては貴族のリゾート地として栄えた街である。ただ、目的はティベリアではない。目的は、ガリラヤ湖畔である。ガリラヤ湖畔は、イエスが布教を本格化させた地である。いよいよ、私はイエスの足跡を追う。ガリラヤ湖畔をまわった後は、ヨルダン川の東岸を下って、エルサレムに入城する予定である。
アッコからはティベリアへの直行バスが無いらしく、一旦ハイファに行ってから、ティベリア行きのバスに乗るしかないそうだ。そこでまずハイファに向かい、ティベリア行きに乗り換えることにする。バスは満席であった。ハイファに向かう途中の景色は、全くと言っていいほど覚えていないが、ハイファ市内に入った情景は覚えている。ハイファは前日に列車内から見上げたが、崖とも言うべき急斜面に街が出来ている。街並みは、やはりどこか欧州風で、イタリアなどにありそうな街並みである。平地を走っていたバスが、わざわざ急坂を登り、客を降ろしていく。最後は、また平地に戻って、平地のバスターミナルに到着する。全く、一度坂を登って、また平地に戻ってくるとはご苦労なことだが、終点のバスターミナルまで乗っていたのは私を含めて3名だけ。いかに街の中心が坂にあるかが分かる。
バスを乗り換え、ティベリアに向かう。乗車率は、大体50%くらいである。途中の景色は、草原に岩がゴツゴツ存在するというもので、何となくカリフォルニアに似た印象である。しかし、これも相応しい表現とは言えない。むしろ「カリフォルニアがここに似ている」と言った方が正確であろう。カリフォルニアは、地中海性気候である。カリフォルニアは地中海沿いではない。したがって、カリフォルニアは、地中海沿岸の景色に似ているのである。どうでもいいことではあるが。
なだらかな草原を、よく整備された高速道路が通っている。周囲は、緑豊かである。これには驚いた。私は、イスラエルはもっと荒涼とした大地であると考えていたからだ。全く砂漠の気配を見せない。しかも、ガリラヤに近づくほど、その土地の豊かさは増す。遠藤作品でイスラエルのイメージを形作ってきただけに、これには「訪れなければ分からない」情景に触れた気がしていた。遠藤周作は、確かに様々な著作でガリラヤの地が豊かであることを触れている。しかし、イエスの時代のガリラヤ地方の人々は貧しく、癩病に苦しみ、娼婦が毎晩自らの惨めさを泣いた地としても描かれている。そのような、陰鬱な描写に接してきた私のとって、これほど豊かな緑が存在するとは思えなかった。目を奪われていたとき、目の前が開け、青い湖面が姿を現す。ガリラヤ湖である。
ティベリアのバスターミナルに降り立つと、宿引きが近づいてくる。学生時代の一時期、このような宿引きを無視して街にずんずん向かっていったものだ。ただそのうちスタイルが変り、複数やってくる宿引きに目の前で競争をさせ、一番条件の良い宿に行くという術を身に付けた。宿引きが必ずしも悪質なものであるケースは少なく、案外信頼できることを知ったからであるが、だからといって警戒しないわけではない。特に治安の悪い地区は要注意で、ガイドブックに載っているような宿に泊まるのが賢明であるが、ティベリアはそうでも無さそうである。今回は、2名の宿引きがやって来た。二人とも、ほぼ同じような条件であったが、決め手はレンタサイクルの有無であった。私は最初に話し掛けてきた宿引きとの交渉に応じ、宿引きの車に乗って宿に向かった。
今回もドミトリーにしたが、ドミトリーは既に先客が入っており、荷物が無造作に置いてある。バックパックであることから、私とそう年齢の変わらない旅行者であろう。私も荷物を置き、フロントで自転車の鍵を借りて、外に出た。
ティベリアは典型的な観光都市である。また、観光都市の中でもかなり栄えており、はっきり言って何でもある。都市とほぼ変わらない生活を送ることが出来る。ただ、先述したとおり、私はあまりティベリアには興味が無い。これはイエスがティベリアに近づかなかったことがそうさせているのかもしれない。ティベリアにはその昔、イエスが近づいた貧民はいなかった。ティベリアは、貴族の街だったのだ。イエスが、そのような人種を毛嫌いしたとか、重視しなかったという消極的な考えもあるかもしれないが、私はティベリアにイエスの慰めが必要な人種がいなかったと考える。つまり、ティベリアにイエスなどいらないと、イエス自身が考えていたのではないか。これはもちろん、遠藤周作の影響を受けた私の予想である。ティベリアにはキリスト教の寺院は確かにあり、十字軍の遺構もあったりするのだが、イエスの伝説を残すものは何一つ存在しない。全く足を踏み入れなかった訳ではないかもしれないが、聖書にもティベリアに足を踏み入れた記録は無い。聖書以外にイエスの行動を示す書籍は無いので、聖書に書いていないということは、現代の我々にはイエスがティベリアに足を踏み入れたと考えることは出来ない。
自転車を借りて、私が向かおうとしたのは、ティベリアから15キロほど離れたところにある、カペナウム遺構である。カペナウムはイエスが伝道の中心としたところである。これは聖書にも書いてある。ただ、聖書に書いてあることが全て真実であると言うわけではないらしく、カペナウムを訪れた可能性は大いにあるが、そこを伝道の中心にしたとは断定できないらしい。しかしながら、ティベリアよりはイエスの痕跡があると断じ、ティベリアからカペナウムに向けて出発した。
ティベリア湖畔は、案外起伏が激しく、周りを山々に囲まれているような印象である。まるで、山中の湖と言う印象である。しかし、ティベリア湖畔の海抜はマイナス209m。つまり、海抜下なのである。周囲の風景からはとてもそうは思えないが、とにかくここは、海面より下である。その土地を、私は汗だくになりながら、坂を上り下りしている。
15キロなど余裕だと思っていたのだが、予想外の起伏によって中々前に進んでいる感じがしない。周囲には民家も無く、自販機も何も無い。水を持ってきて良かったが、汗をかくので余計に疲れる。その内湖畔からも道が離れ、どうも違う方向に進んでいるのではないかと不安になる。私の頼りは、背表紙の黄色いガイドブックのみなのだが、地図が小さくて全く使い物にならない。やはり引き返そうかと思ったとき、目の前に村が見え始めた。標識には"migdal"と書かれている。現在はミグダルであるが、イエスの時代はマグダラと呼ばれた村である。悪霊に取り付かれたマグダラのマリアを、イエスが救ったという伝説の地である。マグダラのマリアは、その後イエス復活の第一発見者として聖書に名をとどめている。イスラエルについて3日目、ようやくイエスの痕跡の残る地にやって来た。