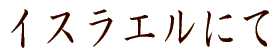 2
2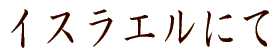 2
2
翌朝、8時くらいに目がさめた。空は晴れ渡り、ホテルの窓からは辛うじて地中海が見える。テルアビブが地中海沿いの街であることを実感する。さて、これからどうするか。ベッドの上で少し考えて、まずテルアビブから出ることを決める。次にどこに行くかである。その時点で私が持っている唯一のイスラエル関連書と言えば、黄色い背表紙のガイドブックだけである。色々な案が自分の頭の中で出てくる。これを少しずつ整理する。いつものパターンである。約10分後くらいには、地中海沿いの街アッコ(Akko,旧名Acre)に向かうため、身の回りの整理を始めた。
バスに乗ってテルアビブ駅につき、早速乗車券を買おうと駅舎に入ろうとする。すると、「ハロー」と言いながら私に話し掛けてくる男がいる。物売りだ。いつものように無視して駅舎に入ろうとする。瞬間、その男に腕を掴まれた。突然だったので当然怯む。一体何だと思い、男の顔を見る。男は口を開き、パスポートを出せと命令する。最初、事情が飲み込めなかったが、どうやらセキュリティチェックのようだ。物売りかと思っていたのだが、公安関係者だったらしい。今まで訪れた国々で、鉄道駅で私服にパスポート提示命令を受けたことはない。共産主義国ですらない。入国時といい今日といい、何とも言えぬ感がある。駅舎の入口で、入国時のような尋問をしばらく受ける。
解放されて、乗車券を買う。乗車券は窓口での対面販売である。イスラエルは決して途上国ではない。近隣諸国に比べたら、かなり発展している。恐らく東欧よりも発展しているであろう。だが、鉄道駅は発展途上国のそれのような構造である。対面販売もそうだが、駅舎全体が燻っているような印象だ。鉄道があまり発達していないのだ。鉄道の発達していない国は、国の発達するスタート時が比較的新しい国である。鉄道の時代に国が発展しなかったため、その名残が無いと思えるからだ。上っ面は発展しているが、実際は若い国であることを印象付けさせる。国の発展の名残と言うものより、英国の植民地時代の名残と言う感じである。
もう一つ、駅舎で気付くことがある。それは兵士の多さである。近隣諸国と常に緊張関係にあるイスラエルは、当然ながら徴兵制が敷かれている。駅舎内の7割までが、徴兵されている若い兵士たちだ。特筆すべきは女性の多さで、ほぼ1対1の割合である。男も女も、全員肩から無骨な銃を下げて歩いている。顔に悲愴感はなく、明るく周りの仲間と話しているので、普通の若者と変らない。だが、肩の銃はその印象をすぐに消す。
列車に乗ってAkkoを目指す。列車はディーゼル車だが、中は広々としていて快適である。コンパートメントにはなっていないが、欧州の列車と同じような車内構造で、対面式でその間に比較的大きなテーブルがある。私の前に座っているのは、私よりも若いと思われる兵士である。テーブルの上にノートを出して、全く訳の分からないヘブル語の文字を書きつづけている。何かの勉強をしているらしい。
車窓は、地中海と白っぽい地盤と、緑の草が続く。ただ、海岸線沿いは低地だが、すぐに崖が迫ってきたりするので、それほど単調ではない。面白いのは家の配置で、何故か新しい住宅はかなり高い崖(というより岩山)の上に建っている。欧州風のアパートメントなので、明らかに居住しているのはユダヤ人だろうが、なぜあんな高いところに家を建てるのか。理解が出来ない。
1時間ほどして、イスラエル第3の都市であるハイファに到着する。ハイファは十分大きな低地がある。だが、やはり町は崖の上に出来ている。ターミナル施設は低地にあるが、居住区は崖の上である。車内から見たに過ぎないのだが、これは帰国して今でも謎である。それから30分ほどして、目的地のAkkoに到着した。
Akkoは、歴史的には4000年の歴史を有しているとのことである。だが、この近辺で4000年の歴史はそれほど珍しくない。何しろ、都市が形成されたのは中東が初めてなのだから。というわけでアッコは4000年の歴史で有名と言う訳ではない。この町は、十字軍の聖地最後の拠点として有名である。十字軍時代の街並みは、後続勢力に蹂躙されたことから、現市街の8メートル地中に埋もれているとのことだ。現在、十字軍時代の遺構は、その通りに地下に存在する。もちろん一般公開されている。現在の市街はオスマントルコ統治時代に形成されたものである。それゆえイスラム建築が溢れており、また、旧市街に居住しているのは殆どアラブ人である。従って、街の雰囲気はトルコの雰囲気が色濃い。と、思って列車を降りた。だが、街の雰囲気は全く異なっており、ドイツの新興住宅街のような雰囲気である。これは駅が新市街に位置しているからである。新市街はユダヤ人の街であるが、旧市街は駅からもう少し歩かなければならない。商店街を抜けるのだが、この商店街など横浜の伊勢佐木長者町のようである。本当に、城壁に囲まれた、モスクが多いアッコがあるのだろうか。
地図に沿って歩くと、いかめしい城壁が見えてきた。堀を越え、城門をくぐる。すると、途端に雰囲気が変る。馬車が闊歩し、騒々しい。街には独特の異臭が漂い、露天商が軒を連ねる。石畳に石造りの建物が並び、迷路のように小路が入り組む。城門の外と中は、ここまで違うものなのか。外は、どう考えてもごく普通のヨーロッパの街だったが、城壁内は完全にアジアである。東南アジアとはかなり異なっているものの、紛れもなく、これはアジアである。入り組んだ小路は、何となくベネチアの印象を抱かせるが、これはかえって逆で私はベネチアがアジアの影響を受けていると思っている。話は逸れるが、イタリアは欧州には珍しく麺(パスタ)や米を食うが、これは交易上アジアと接点が多かったからであろう。中世における交易の中心的な都市国家ベネチアが、中東の街並みに影響を受けるのは至極当然ではなかろうか。閑話休題、とにかく、イスラエルが辛うじてアジアであることを認識させる。
曲がりくねった小路を歩きながら、宿を探す。だが、すぐに路に迷い、方角も何もさっぱり分からなくなる。同じ場所をまわっているように思い、気が付くと波止場に出てしまったりを繰り返す。ようやく宿らしきものの前に出たのは、城門をくぐってから1時間ほどが経ってからである。
相部屋(ドミトリーという)だったので、値段は安かったが、この建物の歴史も古いらしい。今は安ホテルだが、オスマン支配時は何がしかの庁舎だったらしく、内装は薄汚れた高級感を感じる。荷物を置いて、外に出る。
街を散策しながら、何を見るかを考える。最初はモスクに入ったが、礼拝の時間だったので本殿ともいうべき建築には入れなかった。それ以外にも、色々な建物があるのだが、ほとんどがイスラムで、ユダヤやキリスト教の臭いは殆どしない。ただ、キリスト教はこの地面の8m地下に眠っている。モスクの入口の正反対に、十字軍の遺構へ向かう入口がある。そこへ入っていく。
この遺跡が発見されたのは、20世紀の前半だそうだ。英国植民地政府が政治犯を収容する刑務所から、脱走を企てた囚人が偶然地下に逃げ道を掘っていた際に発見したとのことである。戦があると、昔存在した町の上に新しい町を作るのはよくやる手法で、日本でも現在の大阪城の下に、秀吉時代の大阪城郭が眠っているのと同じである。最後に訪れたエルサレムも、歴史を経るごとに年輪のように表層を新たな土が覆っていっている。ここアッコも例外ではない。
遺構の雰囲気は、とにかく暗い。そして、迷路のような小路がある。往時の雰囲気を残す、数々の壁面や天井が見られる。有名なのは、十字の形に組んだ天井だそうで、確かに良く残っている。だが、この遺跡で私が最も覚えているのは、蝙蝠の声である。鼠が叫ぶような声が、暗闇の中から聞こえる。最初、一体何か分からなかった。鼠かと思ったのだが、ひょっとしたらヤモリではないかと思った。ヤモリが鳴くというのは、東南アジアを旅行している人なら誰でも知っていると思うが、その声に似ているのだ。中は湿気臭いし、そうだろうと思った。だが、蝙蝠ではないかというのも、頭に浮かんだ。理由は、羽音がするからだ。遺跡の中には、何故か鳩もいたりしたので、その羽音かとも思ったのだが、暗闇から羽音が聞こえる時点で、「鳥目では飛べまい」と思い、蝙蝠であると断定した。それが当たっていたのは、遺跡内で蝙蝠の遺骸を発見したからだ。両の手でつかめるくらいの小さなものだったが、通常蝙蝠など見ないので、その羽が本当にドラキュラのマントのようであったり、顔が鼠に似ていたり(半分白骨化していたが)と、かすかな光を頼りに、妙な観察を続けてしまった。十字軍がこの地にいたのは12世紀までであるが、蝙蝠は十字軍がこの地を捨ててから、この穴にこもっていたのか。
遺構を出て、また街を歩く。どの街に行っても、大体数時間で地理感覚をつかめるものだが、この街は中々掴めない。これは他の旅行者も同じらしく、幾度となく欧州からの旅行者に道を尋ねられる。だが、こっちもどこにいるのか分からないの「私もgot lostだ」と答える。大抵、お互いに苦笑する。
だが、街の雰囲気はやはり良かった。特に良かったのが夕暮れ時と、暗くなった後だ。イスラエルは地中海の東側に位置するため、全ての海岸線が夕陽が地中海に沈む向きにある。私も、ここの夕陽はきれいだろうと思って、日没直前から海岸部の城壁の上から眺めていた。確かに美しかった。だが、暗くなってからの街はもっと美しい。ライトアップというわけではないのだが、電灯が白熱灯ではなく、おそらくナトリウム灯(トンネルとかにある奴)なので、街の茶色をより引き出すのである。アラブ人地区の夜の人通りの少ない場所はあまり安全とはいえないが、遅くならなければそれほど危険ではない。しばらく歩きつづける。
テルアビブを発ってこの街に来たが、中東の雰囲気を感じることが出来た。なかなかいい街であった。