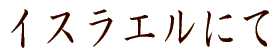 1
1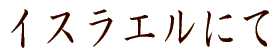 1
1
入国審査に少し手間がかかる。よく分からないが、どうも一人旅の人間に対しては警戒感が強いらしい。ツアー客や、カップルで入国してきた旅行者には殆ど何も言わないのに、どうして一人旅の旅行者だけが脇で同じ尋問を繰り返さなければならないのか。何をしに来た、職業は、今日はこれからどこへ行く、イスラエルではどこを訪れる...?入れ替わり立ち代り、入国審査官が同じ質問を私にしてくる。観光だ、学生だがもうじき卒業だ、テルアビブ市内、まだ決めていない...。出国時の尋問が凄いと言うのは聞いたが、入国でもこんなにしつこいとは聞いていない。しかし、空港では入国審査官には逆らわないし、逆らえない。我慢強く、同じ尋問に、同じ答えを繰り返す。
3人目か4人目の審査官とのお話が終わって、ようやく入国が許される。すでに日付は翌日になっている。空港の案内所で、テルアビブ行きのバスの時間を聞くと、4時間後の朝5時までは無いと言う。5時までここで待つかと聞かれるが、移動時間に20時間ほどかけたため、さすがにどこかに落ち着きたい。だが、空港周辺に経済的な宿泊施設は無いらしい。少し迷ったが、やはりテルアビブに向かうことにした。この深夜に、空港からテルアビブに移動する手段はタクシーかシェルートしかない。シェルートというのは、イスラエル独特の交通機関であるが、要するに乗合タクシーのことで、普通のタクシーよりかなり割安である。ただ、バスよりは高いので、バスがある場合、若い旅行者はバスを利用する。今はタクシーとシェルートしか選択肢が無いので、シェルートを選ぶ。
空港を出て右に歩くと、テントがある。その中には、空港関係者らしき男たちが多くいる。ここでシェルートの券を買うらしい。両替したばかりのイスラエルシュケルを出し、運転手に促されるままにシェルートに乗り込む。客は私一人なので、別段タクシーと変らない。私を乗せたシェルートは空港を出て、120kmを超えるスピードでテルアビブに向かう。運転手は、やや浅黒い顔をしている。アラブ人なのかユダヤ人なのかは判然としないが、そもそも同じセム系の人種である両者の違いが、今しがた当地についた人間に分かる筈も無い。テルアビブに向かう途中で、無線が入る。話口調からどうも仲のよい同業者からの無線らしいが、それがアラブ語なのかヘブル(ヘブライ)語なのかも分からない。私は、後部座席でじっとしているだけである。
空港からの高速道路をおりて、テルアビブ市内に入る。テルアビブの歴史は浅く、まだ街が出来てから100年経っていないそうだ。ただ、イスラエルの建国宣言がこの地でなされ、政府機関は現在はすべて首都エルサレムに移ったとはいえ、経済の中心地として最も現代的な街として栄えていると聞く。テルアビブ市内に入ったときは、すでに午前2時に近いくらいだったが、車は多く、街も明るい。テルアビブはユダヤ人の街である。これがユダヤ人の街かと、車内から外を見る。
ふいに、前を走っていたワゴンが交差点のど真ん中で速度を落とす。ワゴンが完全に止まる前に、中から男たちが出てきて、踊り狂う。すぐさま交差点の四方からはクラクションが激しく鳴り響く。だが、私の乗るシェルートの運転手は黙ってやり過ごそうとしている。その内、男たちがワゴンに戻り、ワゴンは彼方に消えていった。
「何だい、ありゃあ」
車に乗って初めて、私は運転手に話し掛ける。
「〜〜〜地方から来た奴等だよ」
と答える。〜〜〜は聞き取れなかった。というより、知らない地方だった。恐らく、イエスが痕跡を残さなかった地方ではないだろうか。イエスの歩いた地方以外のイスラエルは、私は殆ど知らない。
ガイドブックに書かれているホテル前に車をつけてもらい、シェルートを降りる。ホテルは空室があり、若いユダヤから鍵をもらい、部屋に入る。荷物を置いて部屋を出て、共同シャワーで汗を流す。さっぱりして部屋に戻り、ベッドの上で寝転ぶ。ようやく着いたかと思う。
1996年の11月、あれは大学3年のときである。書店で赤と青のコントラストが美しい表紙を持つ、ある文庫を手に取った。赤いのは、強い夕陽を受けた砂漠の岩山で、青いのは、湖岸の岩に塩の結晶をこびり付かせている死海の湖面である。遠藤周作の「死海のほとり」という小説であったのだが、何故その本を手に取ったのかは理由が曖昧である。表紙がきれいだったこと、タイトルが私にとって突拍子も無かったこと、くらいが理由である。内容は、イエスの行動を小説化したものと、イエスを追う2人の現代人の話である。つまり、キリスト小説である。私にとって全く無縁とも言えるこの世界の小説を手に取ったのは、先述の理由によるのだが、この出会い無くして、私がイスラエルに行こうと思いつくことは無かっただろう。さらに言えば、キリスト者で無い私が、イエスの足跡を追おうとはしなかっただろう。
遠藤周作のこの作品に出会った後、私は遠藤作品の多くを読んだ。60冊程度読んだと思うが、絶版になっている小説も、古書店街を歩いて買い求めたほど夢中になった。2回3回と読み返した本も多い。何が良かったのかと言われると、返答に窮する。具体例を挙げるなら、遠藤作品に見られる次のようなものに、深い感動を覚える。「沈黙」のクライマックスである、主人公の神父ロドリゴが踏絵を踏む瞬間である。
「司祭は足をあげた。足に鈍い重い痛みを感じた。それは形だけのことではなかった。自分は今、自分の生涯の中で最も美しいと思ってきたもの、最も聖らかと信じたもの、もっと人間の理想と夢に満たされたものを踏む。この足の痛み。その時、踏むがいいと銅版のあの人は司祭にむかって言った。踏むがいい。お前の足の痛さを、この私が一番よく知っている。踏むがいい。私はお前たちに踏まれるため、この世に生れ、お前たちの痛みを分つため十字架を背負ったのだ。
こうして司祭が踏絵に足をかけた時、朝が来た。鶏が遠くで鳴いた。」
遠藤作品の描写で私が感動するのは、苦しみぬいた弱者を最後は許す神の存在である。裏切りつづけた弱者を最後は許す神の存在である。遠藤周作の代表作は、これが感じ取られる瞬間が多々あるが、代表作以外でもこのテーマは感じられる。上にあげたシーンも、私はこのような描写で感じ取っている。
趣味が海外旅行だった私は、それまでは特に目的もなく、行きたいところに行っていたが、遠藤作品に出会ってからはそれが少し変った。例えば、香港に行くのに香港をメインにするのではなくマカオに時間を多く割いたり、大学の卒業時にはフィリピンに行ったりである。どちらも、日本でキリスト教が禁教となった江戸時代初期に、多くの切支丹が流れて行ったところである。そして、旅行には必ず遠藤作品を持っていく。マカオの聖ポール天主堂跡の前面壁の前で、目をつぶって夕暮れ時を過ごすという、全く普段の私からは柄でもないことをしたりしてきた。
学生生活が終わりに近づいたある日、私はふとイスラエルに行けないかと思った。大学院に入ってからは、海外旅行は全くしていなかった。だが、卒業前のある日、どうしてもイスラエルに行きたくなった。やはり、遠藤作品の原点とも言える、あのイエスと言う男が歩いた土地を、この目で見てみたいと思うに至ったからである。